「とにかくノートに書きまくる!」「大事なところは蛍光ペンでチェック!」学生時代、誰もが一度は通る道ではないでしょうか。しかし、その“当たり前”の勉強法が、実は科学的に効果が低いかもしれないと聞いたら、あなたはどう思いますか?
この記事では、巷にあふれる勉強法のウソとホントを徹底解剖。日米の医師国家試験にトップクラスの成績で合格した専門家が語る、本当に効果的な記憶術「アクティブリコール」と「分散学習」について、誰にでも実践できるよう分かりやすく解説します。あなたの学習効率を劇的に変えるヒントが、ここにあります!
【この記事の見どころ5段階評価】
- 記憶効率を最大化する「アクティブリコール」の威力:★★★★★
- 忘却を防ぐカギ「分散学習」の重要性:★★★★★
- ついやりがち!「非効率な勉強法」の解説:★★★★☆
その常識、ホントに正しい?「書いて覚える」信仰の光と影
「勉強といえば、ひたすら書くこと」。私たち日本人には、そんな刷り込みがあるかもしれません。北海道札幌市の予備校「実力養成会」代表の今野義之さんも、ある方法で書くことを極め、大きな成果を上げています。
その名も「青ペン書きなぐり勉強法」。これは、予備校・早稲田塾の創業者が考案した記憶術で、青色が持つ心理的効果を利用したものです。
- ストレスを軽減し、心を落ち着かせる効果
- 集中力を高める効果
- 印象に残りやすく、記憶に定着しやすい効果
今野さん自身、この方法で歴史検定日本史1級に合格しており、その効果を実感しています。「やっぱり実際自分の手で書く、口に出すということで定着率は高いです」と語る通り、この方法で東京大学や北海道大学医学部など、数々の難関大学へ生徒を導いてきました。
このように、書くこと自体が全くの無意味というわけではありません。特に、目的意識を持って取り組むことで、大きな力を発揮する場合があるのです。
専門家が警鐘!あなたがやっているかもしれない「非効率な勉強法」
一方で、「書いて覚える」という行為そのものに疑問を投げかける専門家もいます。『科学的根拠に基づく最高の勉強法』の著者であり、現役医師の安川さんは、これまで当たり前とされてきた勉強法の多くが、実は効果が低いと指摘します。
なぜ「ただ書き写すだけ」ではダメなのか?
「黒板や教科書の内容を、そのままノートに書き写す」。この作業、あなたも経験がありませんか?安川さんによれば、この方法は「脳にあまり負荷がかかっていないため、学習効果が低い」とのこと。
確かに、内容を理解していなくても、ただ文字を“作業”として書き写すことはできてしまいます。これでは、勉強した「気」にはなっても、本当に身についているとは言えません。やった気になってしまう、というのが一番の落とし穴なのです。
豆知識「プロダクション効果」: ただし、ただ黙って読む「黙読」よりは、声に出して読んだり(音読)、書き出したりする方が記憶の定着率が良いことも分かっています。これを心理学で「プロダクション効果(生成効果)」と呼びます。単なる書き写しではなく、能動的なアウトプットを意識することが重要です。
「何度も読む」「ハイライトを引く」の落とし穴
では、何度も教科書を読み返す「再読」や、蛍光ペンで線を引く「ハイライト」はどうでしょうか?残念ながら、これらも科学的には有用性が低いと結論付けられています。
- 再読のワナ「流暢性の錯覚」:何度も同じ文章を読むと、内容に慣れてスラスラ読めるようになります。すると、脳は「自分はこれを理解している」と錯覚してしまいます。これが「流暢性の錯覚」です。実際には深く理解していないのに、分かった気になってしまうのです。
- ハイライトの危険性:蛍光ペンで線を引く行為は、どこが重要かを見極める力が必要です。もし見当違いの場所に線を引いてしまうと、かえって学習の妨げになります。実際に、線を引いた部分だけを見直してテストを受けた結果、推論問題の点数が下がったという研究報告もあるほどです。一部分に集中しすぎることで、全体の文脈を見失ってしまう危険性があるのですね。
9回も浪人した経験を持つタレントの浜井さんは、「まさにいっぱい書いてましたし、いっぱいマーカー引いた。むしろ全部引いてました」と語ります。これは多くの人が共感できる「あるある」ではないでしょうか。努力が空回りしないためにも、科学的な視点は非常に重要です。
【本題】日米医師国家試験を制した「科学的に最強の記憶術」
それでは、本当に効果的な勉強法とは一体何なのでしょうか?安川さんが実践し、日本とアメリカの医師国家試験(しかも米国では上位1%)にダブル合格したという驚異的な実績を持つ、その核心に迫ります。
安川さんが最も大切だと語るのが「アクティブリコール」と「分散学習」の2つです。
鍵は「アクティブリコール」!脳から知識を引き出す訓練
アクティブリコールとは、「勉強した内容を、能動的に思い出す(想起する)作業」のこと。情報をインプットするだけでなく、自分の頭の中から頑張って引き出す(アウトプットする)訓練を指します。学習に関する100年以上の研究の歴史の中で、このアクティブリコールが非常に効果的であることが証明されています。
具体的な方法としては、以下のようなものがあります。
- 白紙勉強法:教科書などを読んだ後、一度それを閉じて、覚えた内容を白紙の紙に書き出してみる。
- 練習問題・過去問を解く:知識をインプットした後に、関連する問題を解いてみる。
- 誰かに教える・説明する:学んだ内容を、自分の言葉で他の人に説明してみる。
- 頭の中で思い出す:満員電車の中など、何も開けない状況でも「さっき何を勉強したかな?」と頭の中で復習する。
特に安川さんが活用していたのが「白紙勉強法」です。「やっていただくと分かるんですけど、悲しくなるぐらい覚えてないんですよ」と安川さんは笑います。しかし、この「覚えていない」という事実を認識することが、記憶を定着させる第一歩。分からなかった部分を元の情報で確認し、再度書き出す。この繰り返しが、脳に強力な刺激を与え、記憶を確かなものにしていくのです。
豆知識「プロテジェ効果」: 誰かに教えることで、教えた本人の理解が深まる現象を「プロテジェ効果(教え子効果)」と呼びます。人に分かりやすく説明するためには、自分がその内容をより深く、体系的に理解している必要があります。学校で優秀な生徒が友達に勉強を教えている光景がありますが、実は教えている側が最も効率的な勉強を実践しているのかもしれませんね!
「分散学習」で忘却と戦う!
もう一つの柱が「分散学習」です。これは、「学習する時間を意図的に分散させる、つまり間隔をあけて復習する」という方法です。
ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが提唱した「忘却曲線」をご存知でしょうか。人の記憶は、覚えた直後から急激に失われ、1日後には約7割を忘れてしまうと言われています。
この忘却に抗うのが分散学習です。一度に10時間まとめて勉強するよりも、毎日1時間ずつ10日間勉強する方が、記憶の定着率ははるかに高くなります。忘れかけた頃に思い出す、という行為が、記憶を長期的に保持するための鍵となるのです。
一度で完璧に覚えようとするのではなく、「忘れることを前提に、適切なタイミングで繰り返し思い出す」。これが、効率的な学習の王道と言えるでしょう。
記憶をさらにブーストする!プラスアルファのTIPS
アクティブリコールと分散学習を基本としつつ、さらに記憶効率を高めるためのヒントもご紹介します。
感情と環境を味方につける「記憶の文脈効果」
「この曲を聴くと、あの頃を思い出す」。そんな経験はありませんか?実は記憶は、その時の感情や周りの環境と強く結びついています。これを「記憶の文脈効果」と言います。
例えば、試験本番と同じような静かな環境、同じような時間帯に勉強することで、本番でも記憶を思い出しやすくなる可能性があります。また、浜井さんのように「好きな競馬の競走馬の名前と関連付けて覚える」というのも、ポジティブな感情を利用した優れた方法です。何かを覚えたい時は、五感や感情をフル活用してみましょう!
「なぜ学ぶのか?」モチベーションを高める秘訣
どんなに優れた方法論も、やる気がなければ始まりません。モチベーションを高める上で重要なのは、「その勉強が、自分の人生にどう役立つのか、どう関連しているのかを考える」ことです。
「この公式、将来使わないし…」と思ってしまうと、脳はそれを重要でない情報と判断し、記憶しようとしません。しかし、「この知識があれば、将来こんなことができるかも」と自分事として捉えることができれば、脳はそれを積極的に記憶しようとします。学習を始める前に、一度その価値について考えてみる時間を持つのも良いかもしれません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。これまで信じてきた勉強法が、必ずしも効率的ではなかったと知り、驚いた方もいるかもしれません。
重要なのは、「勉強した気」になるのではなく、脳に適切な負荷をかけることです。今回ご紹介した「アクティブリコール」と「分散学習」は、そのための非常に強力なツールです。
もちろん、青ペン書きなぐり法のように、自分に合っていれば効果を発揮する方法もあります。大切なのは、科学的な知見を参考にしつつ、色々な方法を試して自分だけの「最高の勉強法」を見つけ出すことです。
まずは今日から、学んだことを「何も見ずに書き出してみる」ことから始めてみませんか?その小さな一歩が、あなたの未来を大きく変えるかもしれません!

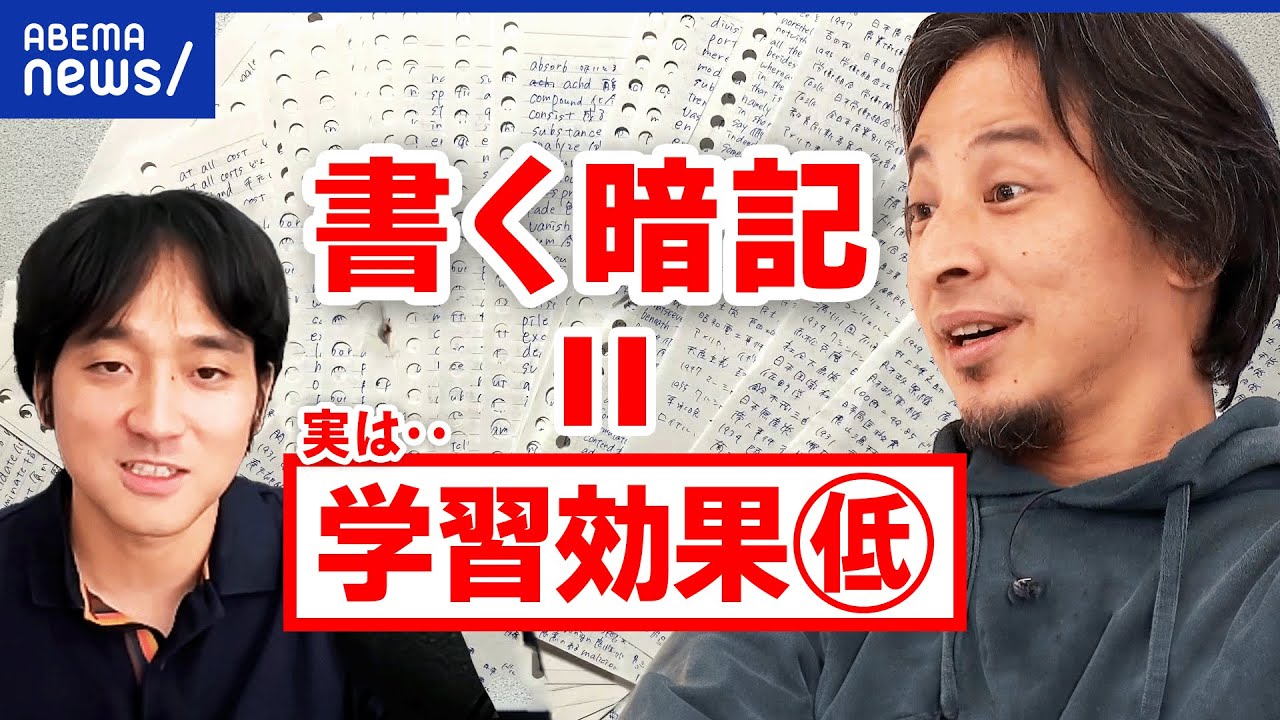

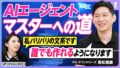
コメント