札幌の市場で朝5時から仕入れを行い、自らトラックを運転し、店頭に立つ社長がいる。彼の名は深沢生活株式会社の代表・深沢社長。
わずか7年で年商17億円を突破しながらも、今も現場に立ち続ける働く社長だ。彼の仕事観は、「稼ぐ」よりも「人を育てる」に根ざしている。
見どころ
この動画で伝わるのは、華やかな成功譚ではない。むしろ「地に足のついた努力と情熱」で築かれたリアルな経営論だ。
- 学べる度:★★★★★
- 共感できる度:★★★★☆
- 人間ドラマ度:★★★★★
豆知識: 深沢社長の祖父は、昭和50年代に札幌でスーパー「マシチェーン商事」を展開した先駆者。いわば商売DNAを受け継ぐ三代目だ。
仕事を「好きになれる人」が勝つ
深沢社長はこう語る。「仕事って、好きにならないと好きな人に勝てない。」この言葉には、単なる精神論ではなく、現場を知る人間のリアリズムがある。
市場では朝5時に仕入れが始まり、100種類以上の野菜が次々に並ぶ。仕入れ価格の交渉、陳列のルール、色の配置。すべてに美学がある。社員たちは「社長のスピード感についていくのが大変」と笑うが、その背中を追うことが、確かな成長の道筋になっている。
現場主義の一日
社長の一日は早い。5時に市場、9時に店舗、昼は販売、夜はミーティング。まるで八百屋のフルマラソンだ。それでも本人は「疲れないんですか?」の質問に、「好きだからね」と即答する。
「社長になったら楽をする」と思われがちだが、深沢社長の考えは逆だ。仕事を誰よりも好きになり、率先して動く。その姿勢が若手たちに火をつけている。
「年収1000万の10人」を育てる方がかっこいい
深沢社長の理念は明快だ。「自分が1億円取るよりも、年収1000万の10人を作る方がかっこいい。」これは一時のスローガンではない。従業員一人ひとりに店を持たせる制度を通して、本気で実現しようとしている。
現在、店長クラスでは年収1200万円を超える人もいる。しかも彼らの多くは20代。特別な学歴も、営業経験もない。ただ、現場で泥臭く、必死に学び続けてきた若者たちだ。
関連情報: 深沢生活では、半年間の研修を経て各店舗に配置。新入社員の多くが「高校卒業後すぐ」に入社しており、平均年齢は25歳前後と非常に若い。
人を育てる経営とは
彼の会社には、「礼儀」「思いやり」「当たり前のことを当たり前にできる」——そんな言葉が日常的に飛び交う。社員教育の根幹にあるのは、人間としての成長が、ビジネスの成長を生むという信念だ。
「人の気持ちを思うこと。それが一番大事。」と社長は断言する。市場での値段交渉も、店舗での接客も、すべては「相手の気持ちを察する力」から始まる。
若手を引き上げる人情リーダー
ミーティングでは社員にこう語る。「もし楽しくなくなったら、それは俺の責任。悩みがあったら、なんでも相談してくれ。キャバクラに行きたかったら、それも誘ってくれ!」——笑いを誘いつつも、その言葉には深い信頼関係がある。
上下関係ではなく仲間意識でつながる職場。社員からも「社長は距離が近くて、怖いと思っていたけど優しい」と声が上がる。
「売上は後からついてくる」ブレない軸
多くの経営者が「売上目標」を掲げる中、深沢社長の発想は逆だ。「目の前の従業員とお客さんを喜ばせていたら、売上は勝手についてくる。」
その哲学が、17億円企業を支えている。従業員が笑いながら働き、客が笑顔で帰る。その循環こそが、深沢生活の最大の資産なのだ。
八百屋というビジネスの進化形
もともとは祖父の代から続くスーパー事業を継ぎ、父が閉店を決意したときに「家賃を払うから俺にやらせてくれ」と始めたのが現在の原点。そこから地道に積み上げてきた成果が今の姿を作っている。
もはや「八百屋」は古い商売ではない。彼が見せるのは、チーム経営と人材育成を核にした令和の商人のモデルである。
経営哲学の核心: 「有名になりたいとか、100億円欲しいとかは後からついてくる。まずは目の前の人を幸せにする。」——深沢社長
「熱量」が若者を動かす
朝5時の市場での仕入れ、手際よい陳列、チームの笑顔、そのすべてが「熱」でできている。若者が惹かれるのは給料の高さではなく、社長の熱量そのものだ。
働くことをかっこいいと感じられる職場は、そう多くない。だが深沢生活には、それがある。数字よりも人を信じ、地道に築き上げたその姿は、まさに現代日本の「情熱経営」の象徴と言えるだろう。

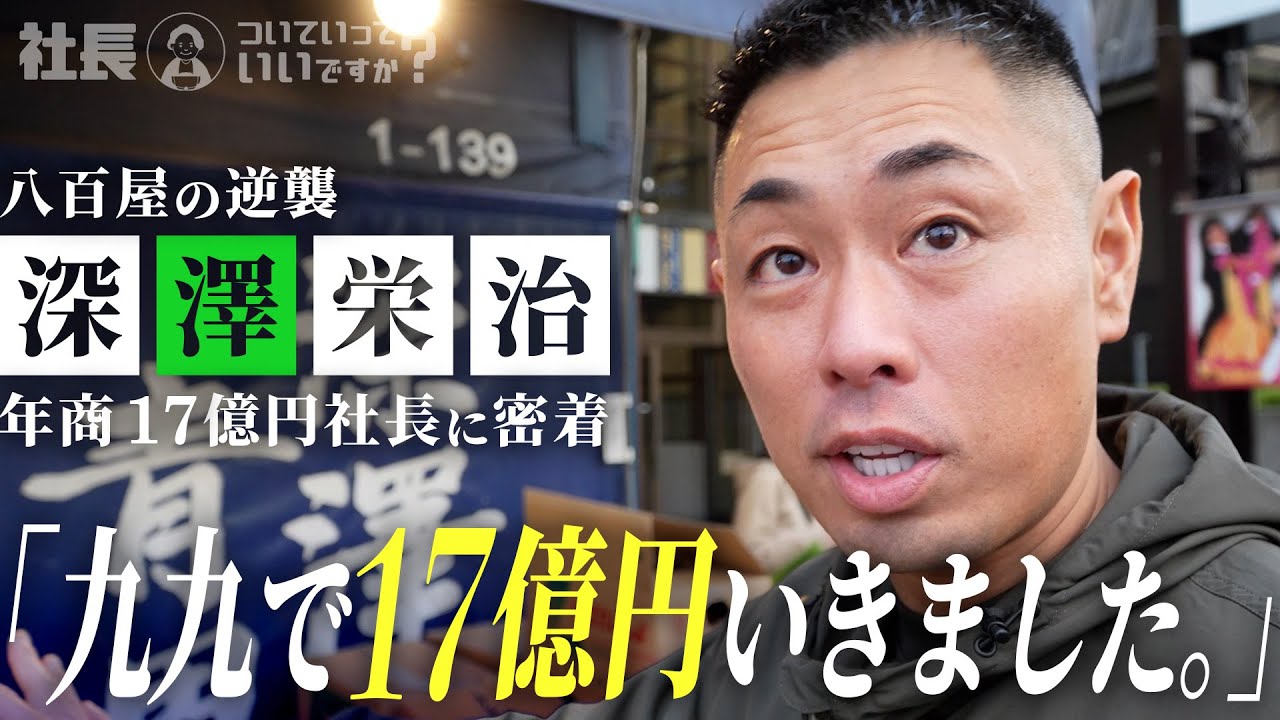


コメント