「若い頃にもっと勉強しておけばよかった…」そう後悔しているあなたに朗報です。実は、大人になってからでも誰でも真似できる、科学的根拠に基づいた最高の勉強法が存在します。この方法は、あなたがこれまでに「勉強は苦手だ」「記憶力がないから無理」と思っていた常識を根底から覆すでしょう。
今回は、安川孝介さんの著書『科学的根拠に基づく最高の勉強法』をもとに、効率的な学習の秘密を解き明かします。
見どころ
・初心者にも分かりやすい解説:★★★★★
・今すぐ実践できる具体的な方法:★★★★★
・勉強のモチベーションを高めるヒント:★★★★☆
あなたの勉強法、実は間違っているかも?
「勉強が大事なのは分かっているけど、自分は頭が悪いから向いていない」「今から勉強してももう遅い」そう思っていませんか? もしかしたら、あなたが勉強できないのは、才能や年齢のせいではなく、やり方が間違っていたからかもしれません。多くの人が無意識に行っている非効率な勉強法が、実は努力を無駄にしてしまっているのです。著者の安川さんは、慶應大学医学部を卒業し、アメリカの医師国家試験にトップ11%以内で合格した秀才ですが、彼自身も「記憶力は良くない」と感じていました。しかし、彼が実践していた勉強法が、後から科学的に証明された最高の勉強法だったことに気づいたのです。
あなたがアメリカの医師になる必要はありません。しかし、この本に書かれた方法を実践すれば、間違いなく勉強の効果を実感できるはずです。
科学的に効果が低い3つの勉強法
まずは、私たちがついやってしまいがちな、「やってはいけない」勉強法を3つ紹介します。これを知るだけでも、あなたの学習効率は劇的に変わるかもしれません。
1. 繰り返し読む
教科書や参考書を何度も繰り返し読む。これ、多くの人がやっていますよね? でも、実はこの方法は科学的には効果が低いと証明されています。コロラド大学の研究によると、文章を2回読んだ学生と1回読んだ学生では、2日後のテストの成績に差が見られなかったそうです。つまり、2回読むために費やした時間は、ほとんど無駄だったということになります。
流暢性の錯覚: 同じ文章を何度も読んでいると、慣れてスムーズに読めるようになります。これを「流暢性の錯覚」といいます。あたかも内容を理解しているかのように錯覚しますが、いざ人に説明しようとすると、何も覚えていないことに気づくはずです。これは、知識が定着していない証拠なのです。
2. ノートに書き写す
学校で黒板に書かれた内容をひたすらノートに写す。これもまた、多くの人が行ってきた勉強法です。アメリカの高校生を対象にした研究では、文章をそのまま書き写したグループは、ただ文章を読んだだけのグループと成績が変わらなかったという結果が出ています。ただ書き写すだけでは、脳にほとんど負荷がかかりません。脳に負荷をかけるためには、要約したり、自分の言葉で書き直したりすることが重要です。
3. ハイライトや下線を引く
「ここ、テストに出るぞ!」と言われると、ついマーカーで線を引いてしまいますよね。しかし、これも実はあまり効果がありません。アメリカの大学生を対象とした研究では、ハイライトしたグループとハイライトしなかったグループでテストの点数に差がなかったという報告があります。さらに、ハイライトを引いている学生の方が成績が悪いという研究結果さえあるのです。
科学的に効果が高い勉強法「アクティブリコール」
それでは、いったいどうすれば効率よく勉強できるのでしょうか? この本が提唱する「科学的に効果が高い最高の勉強法」、それは「アクティブリコール」です。
アクティブリコールとは?
アクティブリコールとは、勉強した内容を能動的に思い出すこと、記憶から引き出すことを指します。私たちはついつい、インプットの量で勉強した気になってしまいます。例えば、「参考書を100ページ読んだAさんより、200ページ読んだBさんの方がたくさん勉強している」と思いがちですよね。しかし、これまでの研究から、インプットばかりの勉強法は非効率であることが明らかになっています。
勉強の効率を上げるためには、インプットした知識をいかにアウトプットするかが鍵となります。アクティブリコールは、まさにこのアウトプットの作業なのです。具体的な方法には、次のようなものがあります。
- 練習問題やテストを解く。
- 白紙に覚えたことを書き出す。
- 誰かに教える。
誰かに教えることで理解が深まることを「プロテジー効果」と呼びますが、教える相手がいなくても大丈夫です。一人でブツブツと呟いたり、紙に書き出したりするだけでも十分な効果があります。
ローディガーとカーピックの研究 (2006年): 14分間かけて文章を何度も読み返した学生よりも、最初の7分間で文章を読み、残りの7分間で内容を思い出す作業(アクティブリコール)を行った学生の方が、2日後や1週間後のテストで明らかに点数が高かったことが報告されています。
この研究結果は、長期的な記憶の定着には、ひたすら読み返すよりも、思い出す作業がはるかに重要であることを示しています。教科書を開かなくても、通勤中や休憩時間など、ちょっとした隙間時間で「さっき読んだ本の要点を思い出そう」と考えるだけでも、立派な勉強になるのです。

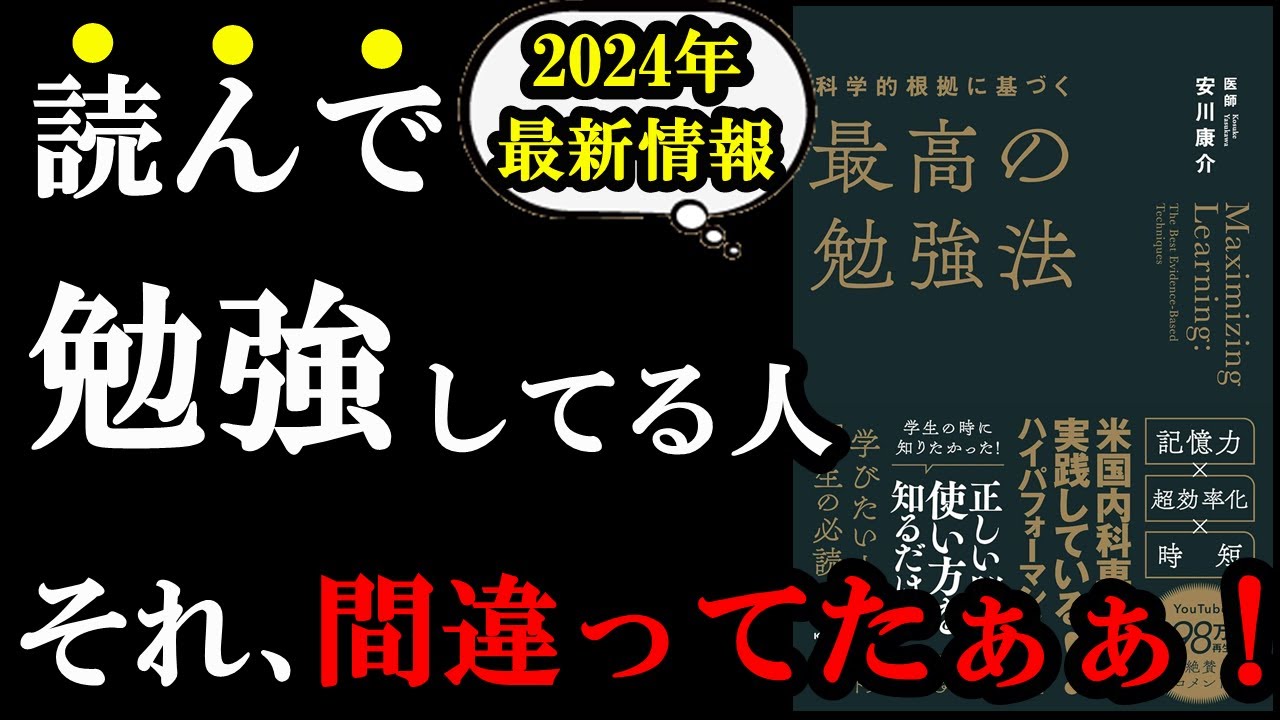


コメント