「隣の土地は倍出してでも買え」。この古くからの不動産格言をめぐって、人気投資家のちょる子さんが真剣に悩み、専門家の牧野さんと語り合いました。舞台は「楽待チャンネル」の特別対談。株で3億円を築いた彼女が、不動産のリアルな壁に向き合う姿が印象的です。
5段階評価と見どころ
- わかりやすさ:★★★★★
- 実用性:★★★★☆
- 不動産市場への洞察:★★★★★
- ストーリー性:★★★★☆
見どころ: 株式投資で成功したちょる子さんが「不動産はタイミングではなく呼吸だ」と気づく瞬間。バブル世代の母との価値観の衝突もリアルに描かれます。
序章:不動産投資家・ちょる子の新たな挑戦
株式投資で資産3億円を築いたちょる子さん。今回のテーマは「自宅の隣の土地を買うべきか?」という極めて現実的な悩み。背景には、母親が長年営む不動産業の経験と、それに基づく「今は絶対に買うな」という強い反対がありました。
母の言葉はこうです。「上がっている時に買ってはいけない。崩れる時は一瞬だから」。昭和・平成バブルの崩壊を経験した世代ならではの警鐘です。
牧野氏の結論:「隣は倍出してでも買え」
牧野氏の回答は明快でした。
「隣地は絶対に買い。倍出してでも抑えるべきです。」
理由は単純かつ論理的。隣の土地を手に入れれば、資産の自由度が飛躍的に高まるからです。
- 既存の家を建て替えやすくなる
- 規模拡大で賃貸経営の収益性が上がる
- 将来の開発・売却時に有利
しかも、ちょる子さんの物件は常南エリア(都内南部)。牧野氏いわく「南と西は東京の鉄板エリア」で、リスクの少ない優良地だと評価します。
母の反対と「平成バブルの記憶」
ちょる子さんの母は、1990年代初頭のバブル崩壊で数多くの人が破産する姿を見てきました。当時の地価は一年で70%上昇、そして一瞬で崩壊。彼女にとって高値掴みは生涯の戒めです。
その記憶が、「路線価より高い価格で買うのはあり得ない」という厳格な投資哲学に結びついています。
豆知識: 路線価とは、国税庁が定める土地の評価額。相続税や贈与税の基準になる数値で、一般的には実勢価格の約8割が目安です。
プロが語る不動産のタイミング論
牧野氏は「価格が高いから買わない」という単純な判断を戒めます。
「隣地が路線価以下に下がるまで待っていたら、誰かに買われてしまう。買うべきタイミングは出た時です。」
さらにアドバイスは続きます。「買ってすぐ建てる必要はない。建築費や円安、人手不足の影響で、今は建てない勇気も大事」。
つまり、今は買って、寝かせる戦略。固定資産税を払いながら、建築費が落ち着くタイミングを待つのが賢明という見立てです。
円安と海外マネー、日本不動産の二重構造
ちょる子さんは「円安と海外マネーが不動産を押し上げている」と分析。これに牧野氏は「短期的には正しいが、長期では危うい」と警告します。
なぜなら、通貨が過度に安い国は経済的に評価されていない国でもあるからです。日本が「買いやすい国」であり続けることは、裏を返せば国力の衰退を意味するのです。
さらに、中国人投資家の動向にも言及。「日本不動産を買っているのは中高年世代。若い世代は日本に興味がなく、次は欧米へ向かう」と中国の富裕層が語ったというエピソードは象徴的でした。
人口減少と相続爆発、2030年の不動産市場
牧野氏が指摘したのは、日本の人口構造の変化です。2030年までに大量の住宅が市場に放出されるという、いわば「相続爆発」期に入るとのこと。
- 首都圏の高齢者は約910万人
- その半数が75歳以上
- 単独高齢世帯は過去20年で3倍
この結果、空き家と中古住宅が急増。需要より供給が増えるため、実需ベースでは価格が下落しやすくなります。
ポイント: 高齢化による売り圧力が出てくるまでの5〜10年が、不動産市場の転換期となる。
ドミナント戦略、「陣地を広げろ」
議論の中で牧野氏が最も力を込めたのが、「ドミナント戦略」の重要性です。
「良い立地では点で持たず、面で抑えること。オセロのように少しずつ隣を取っていく。それが勝ち残る不動産戦略です。」
この陣取り発想は、実際に森ビルや三井不動産など大手デベロッパーが実践してきた戦略。六本木・虎ノ門といったエリアを徹底的に囲い込み、都市開発を主導してきました。
ちょる子さんも「チョルレジ(チョルコ・レジデンス)」を構想し、娘とともに地域の地主として陣地を広げる決意を語ります。
管理こそ資産価値の生命線
不動産の価値を守る要は「管理」と「修繕」だと牧野氏は強調します。
彼が見た東南アジアの事例では、同じ設計で建てられたビルでも、修繕を怠った建物は30年でボロボロに。対して、計画的に維持されたビルは今でも新築同然の状態を保っていたとのこと。
建物は有限だが、土地は無限。この哲学をベースに、世代を超えて資産を引き継ぐには「修繕を惜しまない」「娘と一緒に現場を見る」が最も重要だと説きます。
投資家から地主へ、ちょる子の決断
番組の最後、ちょる子さんはこう語りました。
「もう決めました。チョルコの拠点を作って、陣地を広げます。娘と一緒に、地域の未来を見守る地主になります。」
株式投資のように瞬時のタイミングで勝負するのではなく、「時間とともに育てる」それが不動産の本質だと気づいた瞬間でした。
格言: 隣地は倍出してでも買えは単なる格言ではない。資産形成・相続・地域との関係を含めた長期戦略の核となる考え方である。焦らず、見て、歩いて、育てる。これが不動産投資の王道です。
不動産もまた「人と土地の縁」。チョルコさんのように、冷静な目と情熱を併せ持つ投資家が、次の時代をつくっていくのかもしれません。


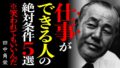

コメント