メガバンク、コンサルティングファーム、監査法人とエリートコースを歩んできたかきけんた氏が、たった一人で創業した会社を約2年半で3.5億円の規模で売却したという驚きの成功事例をご存じでしょうか?
「社員ゼロ、オフィスなし」という、極めてリスクを抑えた形でM&Aを実現したかき氏の戦略と、その裏側に隠された思考法について、詳細に解説します。
かきけんた氏の「成功の景色」5段階評価
かき氏の成功は、単なるM&Aのテクニックにとどまりません。彼が徹底した「自分だけのKPI」の設定や、常識を覆すメディア運営、そして何よりもリスクを限定しながらも大胆に挑戦し続けた姿勢は、多くの起業家やビジネスパーソンにとって、学ぶべき点の宝庫です。皆さんも、きっと「なるほど!」と感じる瞬間が訪れるはずです。
- 見どころ1:常識を覆す「社員ゼロ」経営とM&A戦略:★★★★★
- 見どころ2:独自のKPI設定と「マネタイズは後回し」の思考法:★★★★★
- 見どころ3:リスクを限定しながら挑戦し続ける起業家精神:★★★★★
エリートからの転身:リスクを抑えた起業への道
キャリア迷子からの独立
かきけんた氏は、新卒でメガバンクに入行後、コンサルティングファーム、監査法人といった大手企業で経験を積んできました。しかし、その過程で「会社員に適性がない」という葛藤を抱えていたそうです。いわゆる「典型的な会社員」ではない自分の居場所を模索し、徐々に独立への意識が高まっていったといいます。
多くの人が安定を求める大企業で働く中で、自分の「適性」について真剣に考え、そこから抜け出す決断をするのは、並大抵のことではありません。かき氏のこの初期の葛藤は、私たち自身のキャリアを見つめ直すきっかけにもなるのではないでしょうか。
「労働集約ではない稼ぎ方」への挑戦
独立後、かき氏は人材系のメディア事業、特にSEOを起点とした事業を立ち上げました。なぜ、これまでのキャリアとは一見関係のない分野を選んだのでしょうか?
それは、当時うまくいっているSEOメディアの事例をベンチマークにし、ゼロから独学で学ぶことで、自分でも再現性のある形で成功できると判断したからだそうです。さらに、「労働集約ではない形で、チリンチリン稼げるものを作りたい」という願望があったといいます。コロナ禍以前からリモートワークや自由度の高い働き方を志向していた点は、先見の明があったと言えるでしょう。
また、仮に事業で大きな利益が生まれなくても、Web集客のスキルは自身の「スキル資産」として残り、どこでも生きていけるという確信があったことも大きかったようです。この「ダウンサイドリスクを限定する」という考え方は、リスクを避けがちな私たちにとって、非常に参考になる視点ではないでしょうか。
豆知識: 多くの成功した起業家は、最初に「これは失敗しても得られるものがあるか?」という視点で事業を検討します。スキル習得や人脈形成など、失敗時の「学び」を重視することで、挑戦へのハードルを下げているのです。
「社員ゼロ、オフィスなし」の極限までリスクを抑えた経営
かき氏の事業は、「社員ゼロ、オフィスなし」という、徹底的にリスクを抑えた形態でスタートしました。大企業に新卒で入社するような、本来リスクを取るのが得意ではない人間だからこそ、自身の「リスク許容度」を徐々に高めていった結果だそうです。この「徐々に高める」というプロセスは、いきなり大きなリスクを取るのが怖いと感じる人にとって、非常に現実的なアプローチと言えます。
M&A成功の裏側:独自のKPIとメディア戦略
売上ゼロの1年間:ドメインパワーへの徹底投資
かき氏が創業したメディア事業は、最初の1年間はほとんど収益がなかったそうです。しかし、これは意図的な戦略でした。当時、メディア運営において重要視されていた「ドメインパワー」を高めることに徹底的に注力したからです。売上ではなく、ドメインパワーをKPIに設定し、ひたすら良質な記事を書き、被リンクを獲得する施策に徹したといいます。
これは、目先の利益を追うのではなく、長期的な視点でメディアの「資産価値」を高めるという、非常に戦略的な判断でした。多くのメディア運営者がPV数や広告収入に目が向きがちな中で、収益を完全に無視して「順位」のことだけを考えた結果、その後の急成長につながったのです。
豆知識: SEOにおける「ドメインパワー」とは、Webサイト全体の検索エンジンからの評価を数値化したものです。ドメインパワーが高いサイトは、新しい記事を公開した際にも検索上位に表示されやすくなります。これは、単なるPV数やアクセス数だけでは測れない、Webサイトの「信頼性」や「権威性」を示す指標と言えます。
「1PVの価値」を見極める少数精鋭戦略
かき氏のメディア運営で特に印象的なのは、「1PVの価値」を徹底的に追求した点です。単にPVを集めるだけでなく、それが「お金になる検索結果」から来ているのかどうかを重視しました。転職サイトや転職エージェントの利用を検討しているユーザーからのアクセスは価値が高い一方で、情報収集目的のユーザーからのアクセスは、たとえPV数が多くても収益につながりにくいと見極めたのです。
社員ゼロでリソースが限定されているからこそ、本質中の本質、つまり「センターピン」に集中することで、たった一人でも大企業と戦えると考えました。そして、「普通の人がセンターピンと思っていることとは違う、自分だけのハックを見つけることに快感を覚える」という、かき氏のユニークな思考も成功の要因と言えるでしょう。この「いたずら心のあるハック」こそが、スモールビジネスでPDCAを高速で回す秘訣なのかもしれません。
外部パートナーとの協業:信頼を築くコンテンツ戦略
社員ゼロで事業を運営する中で、記事コンテンツの作成は大きな課題となります。かき氏は、ライターやデザイナーを雇うのではなく、自身でできることは徹底的に学び、血肉にした上で、外部の業務委託メンバーを活用しました。
- デザイナー:業務委託で1名。
- カメラマン:業務委託で1名。
特にユニークなのは、カメラマンを活用した点です。単なるアフィリエイトサイトではない「ちゃんとしたメディア」として信頼性を高めるため、取材記事にはプロのカメラマンによる質の高い写真を掲載しました。これは、大手企業から被リンクを得るための戦略でもありました。取材対象者が「嬉しい」と感じるような、いわゆる「映える」写真ではなく、ブランディング的に爽やかで好印象を与える写真にこだわったそうです。
記事の文章は自身で執筆し、ポット出のメディアだからこそ「圧倒的に質の高い文章」を目指しました。これは、大手企業や権威性のある団体から取材の依頼を受け、信頼を得るための重要な戦略でした。信頼性のあるコンテンツこそが、被リンク獲得、ひいてはドメインパワーの向上につながるということを、かき氏は理解していたのです。
M&Aの舞台裏:交渉術と精神安定剤
「自分にとってのベスト」を追求したM&A
かき氏がM&Aに動き出したのは、創業から約2年が経った頃でした。当時の売上は、良い時期で月2,000万円の利益が出ていたものの、Googleのアルゴリズム変更により月500万円程度にまで落ち込んでいたといいます。個人で持ち直すのは難しいと感じ、M&Aによって「流れを変える」ことを決断しました。
驚くべきは、日本M&Aセンターからの連絡がM&Aを検討するきっかけになったことです。最初に提示された買収額は1億円程度と渋かったものの、「買ってくれる会社がいるんだな」という気づきを得たそうです。そこから、複数のM&A仲介会社に問い合わせ、20社以上と面談。最終的に3〜4社と価格交渉を行い、3.5億円での売却に至りました。
このプロセスでかき氏が重視したのは、「買手候補を複数社いる状態にする」こと。これにより、価格交渉を有利に進められただけでなく、自身の精神衛生を保つ上でも重要だったと語っています。また、売却先となった未来ワークスには、他の買手候補からの条件を本音ベースで伝えていたそうです。これは、仲介会社が間に入ることで「信憑性」が高まり、交渉がスムーズに進む要因になったといいます。
さらに、かき氏はM&A仲介会社を「メンタルケアの人」とも表現しています。M&A交渉は、事業を伸ばしながら進めなければならず、精神的に非常に負担が大きいものです。そんな中で、仲介会社が精神的な支えになるという視点は、M&Aを考えている人にとって非常に示唆に富むのではないでしょうか。
豆知識: M&Aにおける「ロックアップ期間」とは、売却後も一定期間、売却元の経営者が買収先企業に残り、事業運営に関与する期間のことです。これにより、買収先はスムーズな事業承継と、売却元のノウハウ活用を期待できます。
DDは「驚くほど楽」?!リスクマネジメントの徹底
社員ゼロ、オフィスなしの事業形態は、デューデリジェンス(DD)においても大きなメリットをもたらしました。社員も取引先も少なかったため、DDの対象が「事業が今後伸びるか否か」にほぼ限定され、驚くほど楽だったそうです。これは、スモールビジネスやスロプレナー(スモールビジネスをゆっくり育てる起業家)系の事業の利点であると語っています。
契約交渉においては、自身の弁護士への支払いも10万円以下だったといいます。これは、自身で契約書の内容を徹底的に調べ、フォーマットを作成した上で、部分的に専門家に意見を求めるという効率的なアプローチを取った結果です。
さらに、かき氏は売却交渉において、あえて自社の「弱点」や「事業上のリスク」を正直に伝えていました。これは、買手側からすれば「ここまで理解しているのか」という信頼感につながり、むしろ「伸びる可能性」を感じさせる要因になったそうです。上場企業の決算資料に事業上のリスクが細かく記載されているように、リスクを正直に開示することは、相手からの信用を得る上で非常に重要だといいます。
M&A後のキャリア:新たな挑戦と「お金の攻略」
PMIと新たなメディアの成功
売却後、かき氏は未来ワークスのドメイン配下に新たなメディアを立ち上げ、それが見事に成功しました。これにより、M&A後のPMI(M&A後の統合プロセス)もスムーズに進み、爆発的な利益を生み出すことに成功しました。これは、売却先の企業リソースを最大限に活用し、自身のノウハウと組み合わせることで、単独ではなし得なかった成長を実現した好例と言えるでしょう。
特に、未来ワークスの社長が「Webマーケティング関連はかきさんに全部聞いてください」と公言してくれたことが、PMIを円滑に進める上で非常に大きかったそうです。売却後にPMIしやすい立ち位置を、創業者と売却先の社長が共に作っていくことが重要だと語っています。
「分泌活動」への傾倒と「マウント欲求」の経済学
M&Aを成功させ、経済的な不安を解消したかき氏は、現在「執筆活動」に重心を置いています。これまでに複数の書籍を出版しており、2025年もさらに2冊の出版を控えているそうです。特に注目すべきは、企画プロデュースした「人生が整うマウンティング大作戦」という書籍です。
この書籍では、「マウント欲求」、つまり承認欲求がSNS社会で肥大化している現代において、それがビジネスやサービスの成功にどう影響しているかを分析しています。人間の三大欲求を起点にビジネスを考えるように、今後はこの「承認欲求」を刺激する仕組みが、事業を成功させる鍵になると示唆しています。新規事業の観点でも非常に役立つ内容だと語っています。
「お金の攻略」から始まる新たな人生
かき氏は、リスナーからの質問で「資産運用」について聞かれた際、米国債や高格付け企業の社債を組み合わせたETF(上場投資信託)を推奨しています。特にVCLTというETFを例に挙げ、年利5〜6%程度のインカムゲインが得られるとし、非常に安全性が高いと語っています。今後は漫画家や作曲家といったクリエイティブな活動も、SNSとAIを活用することで個人でも実現可能になると予測しています。
かき氏の言葉は、単にお金を稼ぐことだけでなく、「お金の不安をなくし、そこから自分は何をしたいのか」という、より本質的な問いを私たちに投げかけています。お金を「攻略」することで、私たちは時間や場所にとらわれない自由な生活を手に入れ、本当にやりたいこと、つまり自分自身の「人間性」を発揮する道を見つけられるのかもしれません。
かき氏のストーリーは、私たちがお金やキャリアについて考える上で、多くのヒントを与えてくれます。リスクを恐れずに挑戦すること、そして何よりも自分自身の「心の声」に耳を傾けることの重要性を教えてくれるのではないでしょうか。

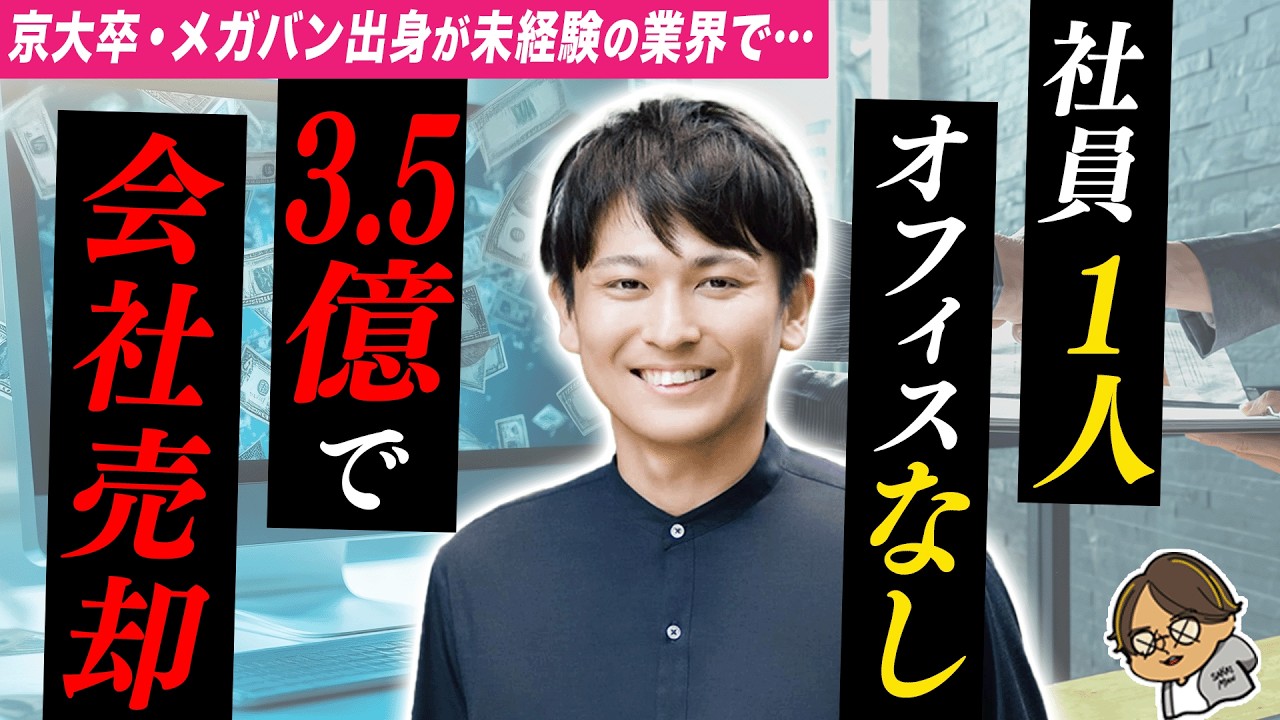


コメント