共通テストの数学、特に二次関数で「もう無理!」と頭を抱えていませんか?ご安心ください!今回は、過去25年分の共通テスト・センター試験を徹底分析して導き出された、二次関数攻略の「絶対解」を皆さんにお届けします。
この解説を読めば、二次関数に対する苦手意識が吹き飛び、「なるほど!」と膝を打つこと間違いなしです。さあ、一緒に二次関数を完全攻略し、周りの受験生に圧倒的な差をつけましょう!
二次関数攻略の5段階評価
二次関数は、グラフのイメージを掴むことができれば、怖いものはありません。この動画で解説されているポイントを押さえれば、共通テストだけでなく、その先の二次試験にも通用する盤石な基礎が築けます。
- グラフイメージの重要性:★★★★★
- 平方完成のスピード:★★★★☆
- 問題パターンへの対応力:★★★★★
この動画の内容を何度も見返し、消化不良を起こさないようにしてください。もし「ちょっと難しいな…」と感じたら、基本的な部分が抜けている可能性があるので、徹底基礎講座で基礎を固めることをお勧めします。
二次関数完全攻略への道:この動画の流れ
この動画では、以下の流れで二次関数を徹底的に解説していきます。
- 共通テストのポイント
- 二次関数の3大頻出パターン
- 共通テストにおける二次関数の出題パターン
- 過去問3年分の爆速解説
過去問解説を通して、この動画で話していることだけで全ての問題が解けることを実感していただけるはずです。
共通テスト攻略の鍵は「グラフのイメージ」
共通テストで二次関数を攻略する上で最も重要なのは、グラフを常にイメージできるかどうかです。グラフをイメージする上で重要な3つのポイントを見ていきましょう。
二次関数の3つの置き方
二次関数には、状況に応じて使い分けるべき3つの基本的な置き方があります。それぞれから何が読み取れるかを理解することが重要です。
- y=ax2+bx+c:
- aの符号:グラフが上に凸か下に凸かを判断します。a > 0 なら下に凸、a < 0 なら上に凸です。
- cの値:y軸との交点、つまりy切片を表します。グラフがy軸とどこで交わるかが一目で分かります。
- y=a(x-p)2+q:
- 頂点の座標:(p, q)が頂点の座標です。グラフの最も高い点または低い点がどこにあるかを把握できます。
- 軸の方程式:x=pが軸の方程式です。グラフの対称軸がどこにあるかが分かります。
- y=a(x-α)(x-β):
- x切片:x軸との交点、つまりx切片がαとβであることが分かります。グラフがx軸とどこで交わるかを把握できます。これは、ax2+bx+cを因数分解した形です。
これら3つの置き方から、それぞれどのような情報が得られるのかを瞬時に判断できるようにしましょう。
平方完成を爆速で行うコツ
y=ax2+bx+cの形から頂点や軸を求めるためには、平方完成が必須です。共通テストでは時間が限られているため、平方完成を素早く行うテクニックを身につけましょう。
例えば、y=3x2+6x+1を平方完成する場合、頭の中で以下のように考えます。
- まず、x2の係数3を括り出すことをイメージします。→ 3(x2+2x) + 1
- 次に、括弧の中を(x+□)2の形にします。xの係数2を2で割って1。→ 3(x+1)2
- このままだと、3(x+1)2を展開したときに3×12=3という余分な定数項が出てきます。これを打ち消すために-3をします。→ 3(x+1)2 – 3
- 最後に、元の式の定数項+1を足します。→ 3(x+1)2 – 3 + 1 = 3(x+1)2 – 2
これで、頂点が(-1, -2)、軸がx=-1であることが瞬時に分かります。文字が含まれる場合でも考え方は同じです。この暗算テクニックを習得すれば、解答時間を大幅に短縮できます。
豆知識:軸の方程式 x = -b/(2a) は、実は解の公式 x = (-b ± sqrt(b2-4ac))/(2a) の「±sqrt(判別式)」の部分を取り除いたものと同じです。グラフの軸は、2つの解のちょうど真ん中にあることを考えれば、この公式を暗記する必要はありません。解の公式を覚えているだけで、軸の方程式も導き出せるのです。
グラフの対称性を常に意識する
二次関数は、軸に関して線対称なグラフです。この対称性を意識することで、様々な問題が解きやすくなります。
例えば、x切片がαとβである場合、軸のx座標は(α+β)/2であることが分かります。これは、αとβのちょうど真ん中が軸になるためです。常にグラフの対称性を念頭に置きながら問題を解くことで、見えないヒントを見つけ出すことができます。
二次関数の3大頻出パターンを徹底攻略
二次関数で特によく出題される3つのパターンを解説します。これらは二次試験対策にも直結する重要な内容です。
二次関数の最大・最小問題
最大・最小問題は、軸のx座標と定義域(範囲)の位置関係を意識することが全てです。グラフを描き、軸と定義域がどのように重なっているかを視覚的に捉えることで、最大値・最小値がどこで取られるかが明確になります。
- 最大値:定義域の端点のどちらかで取られます。軸から遠い方の端点が最大値を与えます。
- 最小値:頂点が定義域に含まれていれば頂点で取られます。含まれていなければ、定義域の端点のどちらかで取られます。
上に凸か下に凸かによっても最大・最小の場所は変わりますが、基本的な考え方は同じです。常にグラフと軸、定義域の位置関係を意識しましょう。
解の配置問題
解の配置問題は、端点、軸、判別式の3つの条件を順番に確認していくことが重要です。これもグラフを書いてイメージすることが不可欠です。
- パターン1:2つの異なる解が正である場合
- 端点:f(0) > 0(y切片が正)
- 軸:軸のx座標 > 0
- 判別式:D > 0(異なる2つの実数解を持つため)
- パターン2:解の片方が正、もう片方が負である場合
- 端点:f(0) < 0(y切片が負)
この場合、f(0) < 0であれば、必ずx軸と正の部分と負の部分で交わるため、軸や判別式を考える必要はありません。端点の条件だけでクリアできる場合があるため、必ず端点から確認するようにしましょう。
平行移動と対称移動
平行移動や対称移動の問題は、頂点の座標とx2の係数の変化を追うことで簡単に解くことができます。
- 平行移動:
- 頂点:移動した分だけ頂点の座標も移動します。
- x2の係数:変化しません。グラフの形は変わらないためです。
- 対称移動:
- 頂点:対称移動の軸に対して頂点の座標が変化します。
- x2の係数:x軸対称移動の場合は符号が反転します。y軸対称移動の場合は変化しません。
グラフをイメージしながら、頂点とx2の係数がどのように変化するかを把握することが重要です。
共通テストにおける二次関数の出題パターン
共通テストでは、二次関数が様々な形で出題されます。主な3つのパターンを見ていきましょう。
利益の問題
「利益 = 売上 – 費用」という基本的な考え方から、売上(値段 × 個数)が二次関数で表されるケースが多く見られます。値段を上げると売れる個数が減る、といった一次関数の関係が組み合わさることで、利益が二次関数になり、その最大値を求める問題が出題されます。
図形の問題
三角形の面積(底辺 × 高さ × 1/2)などが二次関数で表される問題です。底辺や高さが時間の経過とともに変化し、それが一次関数で表される場合に、面積が二次関数となります。
攻略のヒント:図形の問題では、とにかく分かる長さをひたすら図に書き込むことが重要です。これにより、複雑に見える問題もシンプルに捉えることができます。
グラフの読み取り問題
与えられたグラフから情報を読み取ったり、方程式に合致するグラフを選ぶ問題です。特に、不等式と絶対値が絡む問題が頻出です。
- 不等式:例えば「y < 0」であれば、グラフがx軸より下にある部分を考えます。
- 絶対値:場合分けが必要になるため、少し複雑になります。絶対値の中身が正になるか負になるかでグラフの形が変わるため、それぞれの範囲でグラフを正確に描くことが重要です。
これらの出題パターンを理解し、二次関数とどのように絡むのかを把握しておくことで、問題を見た瞬間に解法を思いつくことができるようになります。
過去問解説:実践で学ぶ二次関数攻略
これまで解説してきたポイントが、実際の共通テスト・センター試験でどのように活かされるのかを、過去問を通して確認していきましょう。
2011年センター試験:二次関数の重要パターンが全て詰まった良問
この年は、最大・最小問題、解の配置問題、平行移動・対称移動の問題が全て出題されており、二次関数の重要パターンを網羅的に学習できる非常に良い問題です。多少難易度は高いですが、これを解きこなせれば二次関数は怖くありません。
問題のポイント:
- 軸の一致:「同じ軸を持つ」という条件から、軸の公式 x = -b/(2a) を利用してAの値を求めます。平方完成せずとも軸だけなら瞬時に求められることを確認しましょう。
- 点を通る:「点を通る」とあれば、その点の座標を二次関数の式に代入するだけです。これによりCの値を求めることができます。
- 解の配置:「x軸と異なる2点で交わる」「x軸の正の部分と異なる2点で交わる」といった条件は、端点、軸、判別式の順番で確認します。グラフの向き(上に凸か下に凸か)に注意しましょう。
- 最大・最小:「この範囲における最小値」「この範囲における最大値」といった問題は、軸と区間の位置関係をグラフで視覚的に捉えます。頂点が区間に含まれるか否かで場合分けが必要です。
- 平行移動:「G1をx軸方向にどれだけy軸方向にどれだけ平行移動すればG2と一致するか」という問題は、G1とG2の頂点の座標をそれぞれ求め、その差を計算するだけで解決します。x2の係数は平行移動では変化しないことを再確認しましょう。
この問題を自分の手で解き直し、各ステップでどのような知識が問われているのかをしっかりと復習してください。
2023年共通テスト:一見難解でも基本を押さえれば解ける
この年の二次関数の問題は、平均点が低く「荒れた」と言われましたが、これまでのポイントを押さえていれば、実はそれほど難しくありません。
問題のポイント:
- 放物線の方程式:「P(0,3)とM(4,3)を通る」という条件から、y切片が3であること、そして対称性から軸がx=2であることが分かります。これにより、二次関数の係数を求めることができます。
- シュートの高さ:「最も高くなる時の高さ」は、頂点のY座標を指します。平方完成して頂点のY座標を求めましょう。
- 地上の位置:「最も高くなる時の地上の位置」は、頂点のX座標(軸)を指します。x2の係数が負の場合(上に凸のグラフ)は、軸の式に注意が必要です。
- 点を通る:「放物線C1がDを通る」とあれば、Dの座標をC1の式に代入して、未知の係数(A)を求めます。計算が複雑に見えても、共通因数で括るなどの工夫で簡略化できます。
文章が長く複雑に見えても、結局は「どの点がどこを通るのか」「何が最大値・最小値なのか」といった、二次関数の基本的な性質を問うているに過ぎません。問題文のクリティカルな一文を見抜く力が重要です。
2024年共通テスト:図形問題も基本に忠実に
去年の共通テストでは図形の問題が出題されました。これも、図形問題の基本と二次関数の知識を組み合わせることで解くことができます。
問題のポイント:
- 図形問題の鉄則:「分かる長さをひたすら書き込む」ことを徹底します。時間の経過とともに点の位置や長さがどう変化するかを図に書き込みましょう。
- 面積の計算:斜めの三角形の面積は、台形から他の三角形の面積を引く、といった工夫で求めることができます。
- 二次関数への帰着:時間の関数として面積が二次関数で表されることを理解します。
- 最大・最小:定義域(時間の範囲)における二次関数の最大値・最小値を求めます。点Qが折り返す前後で二次関数の式が変わることに注意し、それぞれの範囲で最大・最小を求め、全体での最大・最小を判断します。
- 不等式:「面積が10以下となる時間」といった問題は、二次関数の不等式として捉え、グラフがy=10の直線より下にある部分のTの範囲を求めます。
図形と二次関数が融合した問題ですが、一つ一つのステップは基本的な内容です。焦らず、丁寧に情報を整理して解き進めましょう。
二次関数は「グラフ」で全てを制す!
いかがでしたでしょうか?共通テストの二次関数は、一見すると複雑に見えるかもしれませんが、「グラフのイメージ」を常に持ち、「3つの置き方」、「平方完成」、「対称性」、そして「3大頻出パターン」をしっかりと押さえることで、どんな問題にも対応できます。
この動画で解説した内容は、共通テストだけでなく、その先の二次試験にも通用する普遍的な知識です。不安な部分は何度も見返し、完全に自分のものにしてください。二次関数を完璧にマスターし、共通テストで高得点を叩き出し、志望校合格を掴み取りましょう!

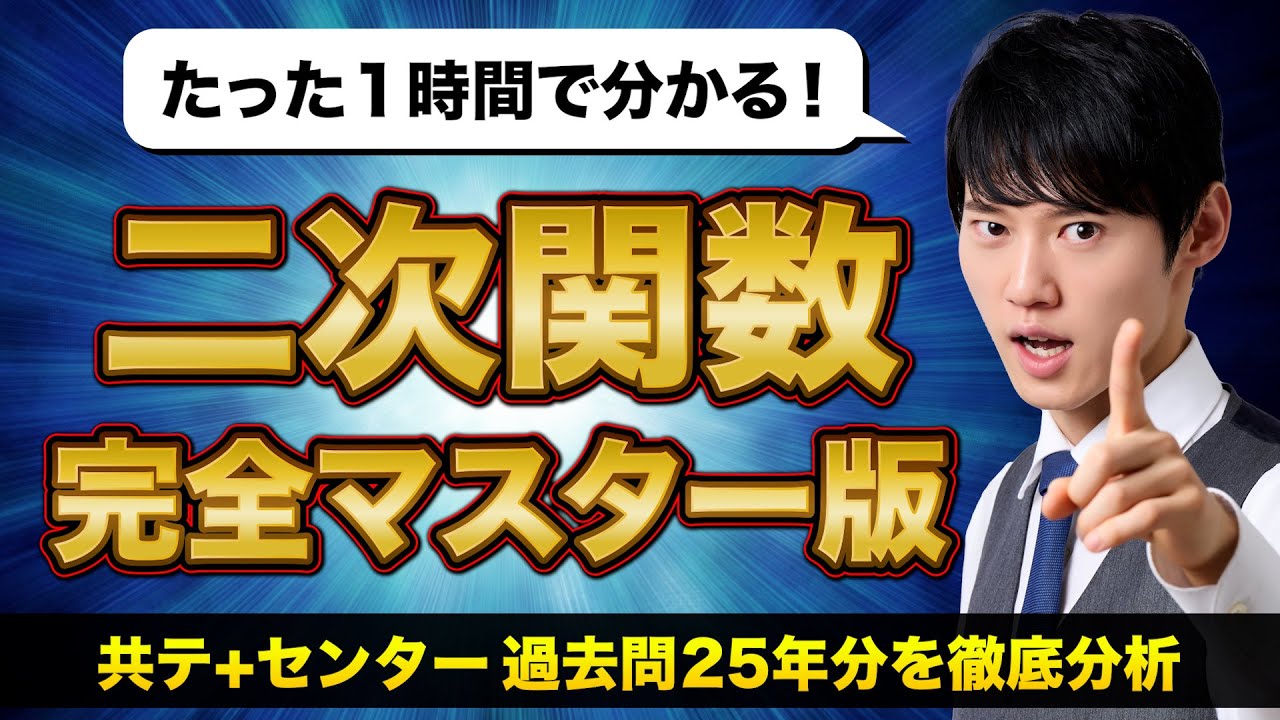
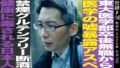

コメント