現代社会は健康ブームの真っただ中。メディアでは「〇〇をすれば健康になる!」「〇〇は体に悪いからやめるべき!」といった情報が日々溢れかえっています。しかし、その過剰な健康意識が、かえって私たちの人生から楽しみや潤いを奪っているとしたらどうでしょう?
今回は、医師でありながら「健康から生活を守る」という逆説的な視点を持つ、大木先生にお話を伺いました。ご自身の経験や医学部での学び、そして数多くの論文を読み解いたからこそ見えてきた「現代医学の抱える問題点」がわかります。
人生の「見どころ」5段階評価!
この動画を通じて、大木先生が提唱する「健康至上主義」への疑問と、それに対する示唆に富んだ考察は、私たちの固定観念を揺さぶり、新たな視点を与えてくれます。特に以下の3点が見どころです。
- 常識を覆す健康観: ★★★★★
- 知的好奇心を刺激する医学的考察: ★★★★☆
- 人生を豊かにする哲学的な問いかけ: ★★★★★
過剰な健康志向に奪われる人間らしさ
大木先生は、現代社会における過剰な健康意識に警鐘を鳴らしています。ご自身の父親が長年ヘビースモーカーであった経験や、子どもの頃に「タバコは体に悪いからやめなさい」と言いつつも、それが当たり前の光景として許容されていた時代を振り返り、「社会に寛容さがなくなっていった」と指摘します。
医学部での学びを通じて、先生はタバコや不健康な食事が体に悪いと教わる一方で、それが患者の人生や楽しみを否定することにつながるのではないかという疑問を抱きました。手術によって日常生活でできなくなることや、治療による患者への負担が教科書に「さらっと」書かれていることに違和感を覚えたと言います。医者は「やりっぱなし」なのではないか、と。
「私たちは健康的な人生観しか認めません、という意味にならざるを得ない」という先生の言葉は、現代社会の健康志向が「健康至上主義」と化し、多様な生き方や価値観を排除しつつある現状を鋭く捉えています。コロナ禍における「ニューノーマル」の押し付けも、まさにその最たる例だと感じました。
豆知識: 喫煙率はかつて男性の8割に達していた時代もありました。今では考えられないような高い水準ですが、当時は家の中でもタバコが当たり前のように吸われていたのです。時代とともに「当たり前」は大きく変化しますね。
タバコを吸う楽しみが、本当にあなたの人生に欠かせないものですか?と問われれば、「そこまでではない」と答える人が多いかもしれません。しかし、「そこまでではないけれど」というものが10も20も重なって、ようやく普通の人の生活が成り立っているのではないでしょうか。それらを一つひとつ「そこまでじゃないから」と切り捨てていけば、果たしてその生活は楽しいと言えるのでしょうか?
先生は、夜更かししてダラダラとスマホを見たり、お菓子を食べすぎたり、つい寄り道してしまったりするような「雑然とした生き方」こそが人間らしさであり、生活の醍醐味だと語ります。何か特定の目的のために最適化された人生は、もしかしたら自分のものではなくなってしまうのかもしれません。「自分の人生そのものが、その目的に奉仕する」という状態は、果たして本当に幸せな生き方なのでしょうか?
医者は弱っている人を助ける立場であり、すべての人に「偉人になれ」とアドバイスするのはナンセンスだという先生の言葉には、ハッとさせられました。過剰なダイエットやアスペルガー症候群の診断が増加している背景には、もしかしたら現代社会のこのような傾向が関係しているのかもしれませんね。
医学は神格化されるべきではない
現代医学は、時に「医療陰謀論」とまで言われることがあります。病気が増えているのは医者が仕事を増やしたいからだ、製薬会社が薬を売りたいからだ、といった見方も存在します。もちろん、それは事実の一面を捉えていることもありますが、先生は「病気を使って自分を語ることのファッション性」という視点も提示します。
文学作品から人生を学ぶ代わりに、医師の言葉を借りて自身のアイデンティティを語る風潮は、文化的に豊かではないと感じるそうです。医学が「自分の生命を最大化する」「なるべく長く生きる」という目標に終始することで、「人生は何のためにあるのか」という問いに答えられなくなってしまうと指摘します。
大木先生が医師免許を取得した理由の一つは、まさにこの「医療の過剰な神格化」に対する違和感からでした。医師の立場になったことで、あえてその「生き方や心のあり方について語る」という役割を「返上」したいと考えたのです。本来、それは医者の仕事ではなかったはずだと。
豆知識: 東大の医学部(理Ⅲ)は、受験勉強の得意な学生が「とにかくトップに行きたい」という目的で進学する傾向があるそうです。そのため、入学してから「本当に医者になりたいのか?」と悩む学生も少なくないとか。意外な裏側ですね。
3万本の論文から見えた現代医学の問題点
大学卒業後、フリーターとして家庭教師をしながら、大木先生は膨大な量の医学論文を読み漁りました。その数、なんと3万本以上。並の医師よりも多くの論文を読んだ結果、現代医学が抱える様々な問題点が見えてきたと言います。
その代表的な例が、血圧の問題です。高血圧を下げるために減塩を推奨されることが多いですが、先生は「あれは嘘」だと断言します。確かに減塩によって血圧が下がったという論文は存在するものの、研究方法によっては錯覚を見ているだけかもしれない、データが偏っているかもしれないといった問題があるそうです。
先生が読み解いたデータによれば、食事の塩分を減らしても血圧はそれほど下がらず、脳卒中や心筋梗塞が減ったというエビデンスもないそうです。それなのに、現代社会では減塩が「とても大事なこと」のように思われている現状に、強い違和感を覚えると言います。
「55%のリスクが53%に減ります、みたいな話だったりするわけですよ」という言葉は、いかに私たちが小さな効果を過大評価しがちであるかを示しています。
日常に潜む「ヤバい毒」との向き合い方
「何でも気持ちいいものは体に悪いって言っちゃえばいいし、何でも不快なものは体にいいって言っちゃえばいいんだ」という先生の言葉には、思わず「なるほど!」と膝を打ちました。努力している人が、努力していない人を見下せるという側面も、健康ブームの一因かもしれません。
「4大毒(小麦粉、油、砂糖、植物油)」といった言葉に代表されるように、現代社会には「体に悪いもの」のリストが溢れています。しかし、それらをすべて断つとなると、私たちが普段食べているものの多くが食べられなくなってしまいます。それは痩せるかもしれませんが、同時に人生の楽しみも大きく奪ってしまうのではないでしょうか?
先生は、酒を「結構ヤバい毒」だとしながらも、「一生で飲める酒の量には限りがあるのだから、ありがたく飲め」という言葉を気に入っていると話します。過剰な飲酒は健康を害しますが、一方で「良くないことをやる権利」もまた、私たちにはあるのです。
「フグの毒ほどのものではない」という言葉に、タバコや飲酒を許容する先生のスタンスが表れています。フグの毒は即座に死に至る可能性がありますが、タバコはそうではありません。どちらも健康に影響を与える可能性はありますが、そのリスクの「大きさ」は大きく異なることを理解する必要があるのですね。
「タイマはタバコより害が少ない」という意見についても触れ、日本では規制が逆転していることの不自然さを認めつつも、あえて規制を緩和することによって何か良いことがあるのかは疑問だと述べています。医療用タイマについても、他の薬で代替できることが多く、必ずしも必要ではないとのことです。
医療が「ヒーロー」であるべきではない社会
現在、高齢者の訪問診療に携わっている大木先生は、その仕事を通じて様々な人生や生活を目の当たりにしています。患者さんの家族関係や価値観を深く知ることで、社会の統計データを見た時にも、その裏にある「生活背景」を想像できるようになったと言います。
しかし、先生は「医療が社会の主役になっちゃいけない」と強く主張します。医療はあくまで社会全体の「セーフティネット」であり、「裏方」であるべきだと。医療がヒーローになる社会は、どこかおかしいと指摘します。
医療の目標は「病気の人を元気にすること」であり、最大限うまくいったとしても「元の生活に戻る」こと。それは「夢がない」と先生は語ります。社会の発展とは、月面着陸を目指すような、もっと夢のある話であるべきだと。コロナ禍で医療や健康を理由に生活が抑圧されたのは、まさに「医療が大事だ」と思いすぎた結果だと分析しています。
ケアの現場に潜む「女性らしさ」の罠
今後、大木先生が書こうとしているのは「女性の役割」についての本です。医療や健康だけでなく、高齢者の介護や子育てといった「ケア」と総称される仕事が、社会通念上「女性の仕事」とされている現状に問題を提起します。
「ケアをする方が女性らしくて、女性として優れている、ということになっちゃう」という先生の言葉は、女性が「女性らしさ」を追求するあまり、ケアが自己目的化してしまう現状を指摘しています。本来、相手のためにするケアが、いつの間にかケアをする自分のためになってしまうという皮肉な現象です。
介護の現場では、高齢者自身が「もういつ死んでもいいから放っておいてくれ」と言っているにもかかわらず、娘さんが「親のためにできる限りのことをしてあげたい」と頑張りすぎて、自分が潰れてしまうケースも少なくないそうです。そして、それが間違った知識に基づいていることもあり、医師から見れば「逆効果」であることも。
「そこはやっぱりこう自分のアイデンティティがかかってしまっているので素直に話が噛み合わないんですね」という言葉に、ケアと女性らしさの結びつきがどれほど根深い問題であるかがうかがえます。先生は、この「ケアと女性との結びつき」を弱めたいと願っています。男性もケアを担うべきだというだけでなく、ケアそのものが特定のアイデンティティと結びついているという考え方自体がおかしいのかもしれない、と。
大木先生の活動は、常に私たちの「当たり前」を揺さぶり、異なる可能性を示してくれます。それは時に波紋を呼ぶかもしれませんが、だからこそ私たちの思考を深め、より豊かな人生を送るためのヒントを与えてくれるのではないでしょうか。

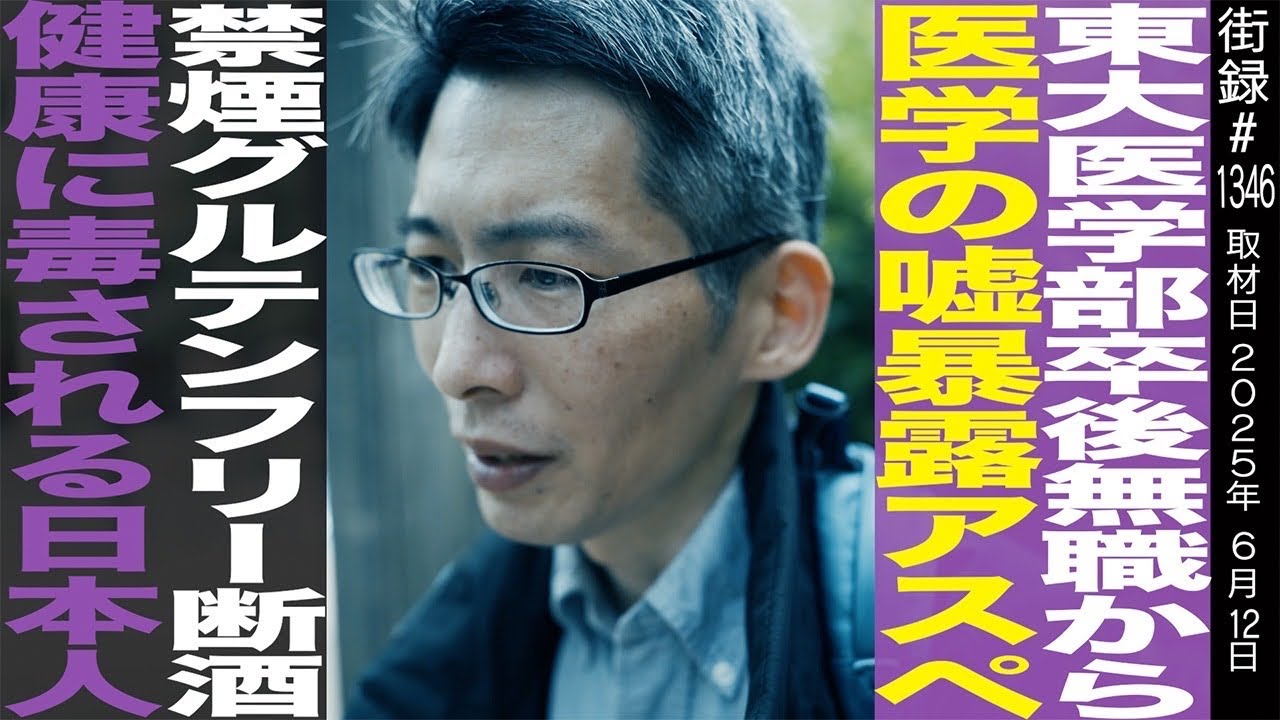

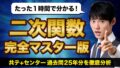
コメント