Python学習者の皆さん、こんにちは!
Pythonを学び始めたものの、環境構築で挫折しそうになった経験はありませんか? あるいは、Google Colaboratory(Googleコラボ)を使っているけれど、その真のポテンシャルをまだ引き出せていないと感じている方もいるかもしれませんね。
今回は、そんな皆さんの悩みを一掃する、Googleコラボ完全攻略ガイドをお届けします。この動画を見れば、もうGoogleコラボで困ることは二度とありません。Python学習の効率が2〜3倍アップすること間違いなしです!
Google Colaboratory 5段階評価
Googleコラボは、まさにPython学習者の強い味方です。無料でこれだけの機能が使えるなんて、Googleさん、太っ腹すぎませんか?
- 手軽さ:★★★★★
Pythonのインストール不要で、Googleアカウントがあればすぐに始められます。 - 高機能:★★★★★
通常なら数十万円するGPUが無料で使え、本格的なデータ分析にも対応できます。 - 共有のしやすさ:★★★★★
Googleドキュメントやスプレッドシートのように、リンク一つで簡単にコードを共有できます。
見どころは、なんといっても「無料で高性能なGPUが使える」点でしょう。ディープラーニングのような計算負荷の高い処理もサクサク行えるのは驚きです。また、コードの共有が驚くほど簡単なのも魅力ですね。チームでの共同作業はもちろん、友達にちょっとしたコードを見せるのも非常にスムーズです。
Google Colaboratoryとは?
そもそも、Googleコラボとは一体何者なのでしょうか? Google Colaboratory、通称Googleコラボは、ブラウザ上でPythonを実行できるGoogleが提供するサービスです。「え、ブラウザでPythonが動くの?」と驚いた方もいるかもしれませんね。
無料で使える魔法のツール
通常、Pythonを使うには自分のパソコンにPythonをインストールする必要があります。これが初心者にとって最初のハードルとなりがちですよね。しかし、Googleコラボがあれば、その環境構築の苦労から完全に解放されます。Googleアカウントさえ持っていれば、スプレッドシートやGoogleスライドを使うのと同じ感覚で、誰でも無料でPythonを実行できる環境が手に入るんです。
「無料なのに本当に大丈夫なの?」と思う方もいるかもしれません。もちろん、無料プランにはリソースの制限はありますが、個人のPython学習やデータサイエンスの入門レベルであれば、全く不自由なく利用できます。例えるなら、食べログで有料会員にならなくても、十分に美味しいレストランを探せるのと同じ感覚です。データサイエンスや機械学習を始めるために、いきなり高スペックなパソコンを買う必要はありません。まずはGoogleコラボでPythonの世界に飛び込んでみましょう!
豆知識: Googleコラボは、データサイエンスでよく使われるJupyter Notebookをベースにしています。そのため、Googleコラボの操作に慣れれば、実務でよく使われるJupyterの操作も自然とマスターできますよ。
Google Colaboratoryのメリット
Googleコラボの最大の魅力は、その豊富なメリットにあります。具体的には以下の3点が挙げられます。
1. Pythonのインストールが不要
これは、Python学習者にとって最も大きなメリットと言えるでしょう。Pythonの環境構築は、多くの初心者にとって最初の挫折ポイントになりがちです。Anacondaのインストールに苦戦したり、複数のインストール方法に頭を悩ませたり…そんな経験、ありませんか?
Googleコラボを使えば、そんな心配は一切不要です。Google ChromeやSafari、Microsoft Edgeなど、普段お使いのブラウザでインターネットに接続できれば、それだけでPythonを実行できる環境が整います。「たったこれだけでPythonが動くの!?」と感動すること間違いなしです。
2. コードの共有が簡単
皆さんは、自分が書いたPythonコードを誰かに見てもらいたい時、どうやって共有していますか? ファイルをメールで添付したり、チャットで送ったり…正直、面倒ですよね。特に、コードを少し修正するたびにファイルを送り直すのは、送る側も受け取る側もストレスが溜まります。
プログラミングの世界ではGitやGitHubといったバージョン管理ツールがありますが、これを習得するにはそれなりの時間が必要です。Python初心者のうちは、とにかくコードを書くことに集中したいですよね。
Googleコラボなら、そんな煩わしさとは無縁です。GoogleスプレッドシートやGoogleスライドのように、画面右上の「共有」ボタンをクリックしてリンクを教えるだけ。難しい知識がなくても、驚くほど簡単にコードを共有できます。これにより、学習中のコードレビューもスムーズになりますし、将来的にデータ分析のコンペティションに参加する際も非常に役立ちます。
3. GPUも無料で使える
「GPUって何?」と思った方もいるかもしれませんね。GPUとは「Graphics Processing Unit」の略で、画像や動画の処理に特化したパーツのことです。例えるなら、一般的な処理を行うCPUが人間の脳だとすると、GPUは単純な計算を大量にこなすことに特化した「計算のスペシャリスト」のような存在です。
このGPUが、特にディープラーニングのような大量の計算が必要な機械学習において、絶大な威力を発揮します。本来なら、GPUを内蔵した高価なパソコンを購入したり、別途GPU環境を構築したりする必要があるのですが、Googleコラボなら、なんとこのGPUすらも無料で使えてしまうんです!
以前は「無料だから性能もそれなりでしょ?」と思われがちでしたが、Googleコラボで提供されているGPUの性能は年々グレードアップしており、今では普通に購入すると数十万円する「Tesla T4」というGPUを無料で利用できます。これは本当に衝撃的ですよね。もちろん、有料プランにアップグレードすればさらに高性能なGPUを使えますが、Python学習を始めたばかりの方には全く必要ありません。まずは無料の範囲で、この高性能なツールを最大限に活用しちゃいましょう。
Google Colaboratoryのデメリット
Googleコラボは非常に優秀なツールですが、完璧ではありません。強いて言えば、以下の3つのデメリットが挙げられます。
1. データの読み込みに手間がかかる
例えばCSVファイルを読み込みたい場合、自分のパソコンでPythonを使っていれば、コード1行で済むことも多いでしょう。しかし、Googleコラボはブラウザ上で動作するツールのため、自分のパソコン上のファイルを直接操作することはできません。
Googleコラボでファイル操作を行うには、まずGoogleドライブにCSVファイルをアップロードし、次にGoogleコラボからGoogleドライブにアクセスできるように設定し、最後にPythonコードでCSVを読み込む、という手順を踏む必要があります。少しステップが増えてしまいますが、操作自体は難しくないので、すぐに慣れるはずです。
2. 時間に制限がある
Googleコラボには、具体的に90分と12時間という2段階の利用制限があります。
- 90分ルール: 何も操作せずに90分経過すると、セッションがリセットされます。これは、ノートブックの「起動状態」がリセットされるという意味で、定義した変数などがクリアされます。しかし、ノートブックに書いたコード自体は残るのでご安心ください。
- 12時間ルール: 作業中かどうかにかかわらず、12時間経過すると強制的にノートブックがリセットされます。
「90分しか使えないの!?」と不安になるかもしれませんが、これはあくまで何も操作しない場合のリセットです。積極的にコードを書いていれば問題ありません。変数の状態をクリアしたい時など、意図的にランタイムをリセットする機能としても活用できます。この点は、後ほど詳しく解説します。
3. 容量に制限がある
Googleコラボで作成したノートブックや読み込みに使うデータは、Googleドライブ上に保存されます。つまり、Googleコラボで使える容量はGoogleドライブに依存するわけです。無料ユーザーの場合、Googleドライブの上限は15GBです。15GB以上の容量を保存したい場合は、Googleドライブの有料プランに課金する必要があります。
しかし、正直なところ、よっぽど大規模なデータを取り扱わない限り、15GBで不足することはありません。Python学習の初期段階であれば、このデメリットはあまり気にする必要はないでしょう。
Google Colaboratory vs Jupyter Notebook
「データ分析や機械学習を勉強するなら、Jupyter LabやJupyter NotebookとGoogleコラボ、どちらを使えばいいですか?」という質問は、私もよく受けます。
結論から言うと、どちらでも大丈夫です。なぜなら、Googleコラボも結局はJupyter Notebookをベースにしているからです。現場ではAWSやGCPなどのクラウドサービスで分析環境を構築するケースが多いので、自分のパソコンにJupyterを入れるか、Googleコラボを使うかに大きな差はありません。
重要なのは、使うツールにこだわることではなく、データ分析のスキルや機械学習、統計学の基礎を習得することです。業務効率化を目指すなら、Pythonを使ったExcel操作やスクレイピングの基礎を学び、さっさと自動化することが最優先です。
不要な学習を避け、優先順位を決めて学習を進めることで、驚くほど早く成果を出すことができます。この動画でGoogleコラボの使い方をマスターして、Pythonやデータ分析の基礎学習をすぐに始めましょう!
Google Colaboratoryの使い方
それでは、いよいよGoogleコラボの具体的な使い方をご紹介していきます。まずは、ノートブックの作成から始めましょう。
1. ノートブックの作成
Google検索からGoogleコラボを開く方法もありますが、今回はGoogleドライブからノートブックを作成する方法を解説します。
- Googleドライブにアクセスします。
- ノートブックを保存したいフォルダ(例: Googleコラボマスター)を開きます。
- 「新規」をクリックし、「その他」から「Google Colaboratory」を選択します。
もし「Google Colaboratory」が表示されない場合は、「アプリを追加」をクリックし、アプリ検索で「Googleコラボ」と検索してインストールしてください。インストールが完了すれば、上記の手順で新しいノートブックを簡単に作成できます。「Untitled0.ipynb」という名前で新しいノートブックが作成されましたね。
2. コードの入力と実行
Googleコラボでは、「セル」と呼ばれるブロックにコードを入力していきます。カーソルが当たっている白い部分がセルです。
- セルの中に「
A = 1 + 2」と入力します。 - コードを実行するには、セルの左にある再生ボタンをクリックします。
初回はセッションへの接続に時間がかかりますが、しばらくするとチェックマークが付き、コードが実行されます。これで変数Aに「1 + 2」の結果が代入されました。
変数Aの中身を確認するには、同じセルに「print(A)」を追加してもう一度再生ボタンをクリックします。すると、結果として「3」が出力されますね。これがコードの入力と実行の基本的な流れです。Python初心者の方には、「プログラミングってこんなに手軽なの!?」と感動するかもしれませんね。
3. セルの追加とテキストの記入
「じゃあ、もっとセルを追加するにはどうすればいいの?」そう思いますよね。セルを追加するのも簡単です。画面左上の「+ コード」をクリックするだけで、新しいコードセルが追加されます。
また、Googleコラボでは、コードだけでなくテキストを記入するための「テキストセル」も追加できます。これは、コードの解説や気づいたことをメモするのに非常に便利です。「+ テキスト」をクリックすると、コードとは違う表示のセルが追加されます。テキストセルには好きな文字を入力でき、入力後はEscキーを押すだけで保存されます。データ分析中に気づいたことをメモしておけば、後から見返すときに非常に役立ちますよ。
4. ライブラリの利用とインストール
Pythonの魅力の一つは、豊富なライブラリですよね。Googleコラボでは、データ分析でよく使うPandasや機械学習でよく使うscikit-learnなど、主要なライブラリがあらかじめインストールされています。
試しにコードセルを追加して、「import pandas as pd」と「import sklearn」と入力し、再生ボタンをクリックしてみてください。ライブラリのインポートに成功するはずです。さらに、「print(pd.__version__)」を実行すれば、Pandasのバージョンを確認できます。
ただし、あまり使われていないマイナーなライブラリは、あらかじめインストールされていません。その場合は、自分でライブラリをインストールする必要があります。
例えば、「Wikipedia」というライブラリをインストールしたい場合、コードセルに「!pip install wikipedia」と入力して実行します。コマンドを実行する際は、通常のコードと区別するために先頭に「!(ビックリマーク)」を付けます。これで、Wikipediaライブラリがインストールされ、使えるようになります。もしエラーが出たら、焦らずにこの方法を試してみてくださいね。
5. 見出しの作成と目次機能
テキストセルでは、ただメモを記述するだけでなく、見出しを作成して目次として活用することもできます。これは、長文のノートブックを整理する際に非常に便利な機能です。
- 左サイドバーにある3本線(セクション)をクリックします。
- 「新しいセクションを追加」をダブルクリックします。
- 追加されたテキストセルに見出しとして記述したい内容(例: 「ライブラリのインポート」)を入力します。
このように見出しを作成しておけば、目次一覧から該当する見出しまでワンクリックでジャンプできます。特にデータ分析では、各項目ごとにコードを参照したい場面が多いので、積極的に目次機能を活用しましょう。
豆知識: テキストセルで「#」の後に半角スペースとテキストを入力することでも見出しを作成できます。例えば、「# データ分析」と入力すると、見出しとして認識されます。慣れてきたらこちらの方法も試してみてください。
6. ランタイムのリセット
「ランタイム」とは、ノートブックが起動している状態のことです。Googleコラボのデメリットで説明した90分ルールは、このランタイムのリセットを指しています。
ランタイムの起動中は、ノートブック内で定義した変数をいつでも使うことができます。しかし、ランタイムを停止したり再起動したりすると、定義した変数の状態はリセットされます。例えば、変数Aに値を代入した後、ランタイムを再起動すると、変数Aは「定義されていません」というエラーになります。
ランタイムのリセットは、例えば変数の状態を完全にクリアしたい時などに使用します。画面上部のメニューから「ランタイム」→「ランタイムを再起動」をクリックするだけで実行できます。今は「リセットする方法があるんだな」と覚えておけば大丈夫です。
7. GPUの設定
Googleコラボの大きなメリットであるGPUは、自分で設定しないと使うことができません。しかし、設定方法は非常に簡単です。
- 画面上部のメニューから「ランタイム」→「ランタイムのタイプを変更」をクリックします。
- 「ハードウェアアクセラレーター」が「なし」になっているはずなので、これを「GPU」に変更します。
- 無料版の場合、GPUのタイプは「T4」が選択されていることを確認し、「保存」をクリックします。
たったこれだけでGPUを使えるようになります。ただし、GPUに切り替えると以前のランタイムが削除されるため、途中まで実行していたコードがリセットされてしまいます。そのため、GPUを使いたい場合は、コードの入力や実行を開始する前に切り替えておくことをおすすめします。
GPUが正常に切り替えられたか確認するには、コードセルに「!nvidia-smi」と入力して実行します。「Tesla T4」と表示されれば、GPUが利用可能な状態になっています。ディープラーニングの勉強をする際は、この方法でGPUに切り替えてみてください。
8. ノートブックの共有
Googleコラボでは、スプレッドシートやGoogleスライドのように、ボタン一つで作成したノートブックを共有できます。しかも、やり方は非常に簡単です。
- 画面右上の「共有」ボタンをクリックします。
- 共有したい人のメールアドレスを追加するか、「一般的なアクセス」を「リンクを知っている全員」に切り替えることで、リンクを知っている人なら誰でもアクセスできるようになります。
これなら、会社の同僚にデータ分析の結果を共有する際も、リンク一つで簡単に集計結果や作成したグラフを見てもらうことができます。別途PowerPointを作成する必要もなくなるので、業務効率化にも繋がりますね。
9. ノートブックのダウンロードとアップロード
GoogleコラボはJupyterをベースにしているため、ノートブックをダウンロードして自分のパソコンで使ったり、自分のパソコンで分析したノートブックをGoogleコラボで使ったりできます。
ダウンロード
ノートブックをダウンロードするには、画面左上の「ファイル」→「ダウンロード」→「.ipynb をダウンロード」をクリックします。これで、今使っていたノートブックを自分のパソコンに保存できました。あとは、手元のパソコンでJupyterを起動し、保存したノートブックを開くだけです。
アップロード
自分のパソコンで作成したノートブックをGoogleコラボで使うには、まずGoogleドライブにファイルをアップロードします。Googleドライブにファイルをアップロードしたら、そのファイルをダブルクリックで開いてみてください。Googleコラボで問題なくファイルを開けるはずです。
私のYouTube動画や市販の書籍で学習する際、ノートブックが添付されていることが多いですよね。そんな時、Googleコラボを使って学習を進めていくなら、この手順を参考にファイルをアップロードしてみてください。
Google Colaboratoryの注意点
Googleコラボの基本的な使い方をマスターしたところで、非常に重要な注意点を一つご紹介します。それは、「一つのセルで定義した変数が別のセルでも使える」ということです。
これは一見メリットのように思えますが、Python初心者にはデメリットになるケースがあります。それはどんな時だと思いますか?
正解は、「sum」のようなPythonで予約語として使われる名前を変数名として使うときです。
具体的に見てみましょう。まず、コードセルに「sum = 1 + 2 + 3」と入力し、その結果を変数「sum」に代入します。そして「print(sum)」と実行すると、問題なく「6」と出力されます。
しかし、後から「[1, 2, 3]というリストの要素を全て足し合わせたい」と思った時に、Pythonの基礎を学んだ方なら、リスト内の数字を足すには「sum()」関数を使うことを知っていますよね。そこで、別のセルで「result = sum([1, 2, 3])」と入力して実行すると、なんとエラーが発生します。
これは、本来「sum」が関数名として機能するはずなのに、先に「sum」を変数名として使ってしまったため、関数としての役割が上書きされてしまったために起こるエラーです。このエラーは、私も過去に指導してきて、少なくとも50回は質問されました。
Pythonには「sum」や「str」、「id」、「int」のように、あらかじめ役割が決められている名前(予約語)が多数存在します。これらの名前を変数名として使うのは、絶対に避けましょう。もしPythonコードの書き方に不安があれば、予約語について調べてみることをおすすめします。
Google Colaboratoryのショートカットキー17選
ここまでで、Googleコラボについてかなりの理解が深まったと思います。もうあとは、Googleコラボを使いこなしてPython学習を加速させるだけですね!
「毎回セルを追加するのは大変だな」「コードを実行するのに再生ボタンを押すのは面倒だな」と感じた方もいるかもしれません。そこで、ここではGoogleコラボの作業効率を劇的に上げるショートカットキーを17選ご紹介します。これらを全て習得すれば、作業効率が少なくとも3倍以上になるはずです。ぜひ全てマスターしてしまいましょう!
よく使う基本ショートカット
Shift + Enter: セルを実行し、下に新しいセルを追加します。これからは再生ボタンではなく、このショートカットを使い倒しましょう!Ctrl + Mの後にB: 現在のセルの下に新しいコードセルを追加します。Ctrl + Mの後にM: 現在のコードセルをテキストセルに変更します。Ctrl + Mの後にY: 現在のテキストセルをコードセルに変更します。Ctrl + Mの後にD: 不要なセルを削除します。Dは「Delete」の頭文字なので覚えやすいですね。Ctrl + Mの後にZ: 誤って削除したセルを元に戻します。Esc: セルの編集を終了し、セルから離脱します。- 上下矢印キー: セルから離脱した状態で、カーソルを上下に移動します。
Enter: 選択しているセルの編集を開始します。
複数セル操作・実行ショートカット
Shift + 上下矢印キー: 複数のセルを選択します。Ctrl + C: 選択したセルをコピーします。Ctrl + V: コピーしたセルを貼り付けます。Ctrl + Mの後にK: 選択したセルを上に移動します。Ctrl + Mの後にJ: 選択したセルを下に移動します。Ctrl + F9: 全てのセルを実行します。Ctrl + F8: 現在のセルよりも前の全てのセルを実行します。Ctrl + F10: 現在のセル以降の全てのセルを実行します。
その他便利ショートカット
Ctrl + S: ノートブックを保存します。Googleコラボは自動保存されますが、念のためこまめに保存する癖をつけましょう。Ctrl + Mの後に.(ピリオド): ランタイムを再起動します。確認のポップアップが表示されたら「はい」を選択します。
これらのショートカットを使いこなせば、驚くほど効率的に作業が進むはずです。何度も練習して、完璧にマスターしてくださいね。
Colabのパイソン
いかがでしたでしょうか? Google Colaboratoryのメリット、デメリット、使い方、そして作業効率を劇的に上げるショートカットキーまで、Python学習に必要な情報はほとんど網羅できたと思います。
ここまで動画を見てくださった皆さんなら、もうPythonを習得できるはずです。だって、1時間も2時間もこの動画を見続けているのですから、それだけのガッツがあれば、これからPython学習をさらに加速させていく皆さんは、絶対に挫折しないし、何よりも絶対に負けません。
もし途中でくじけそうになったら、またこのチャンネルに戻ってきてください。コメントを残していただければ、私が一つずつ丁寧に返信しますので、それを見てやる気を出してほしいです。自分を信じて、一日30分でもいいから、昨日の自分に勝っていれば大丈夫です。周りのことは気にせず、自分のペースで学習を絶対にやめないこと。そうすれば、必ずPythonを習得できるようになります。

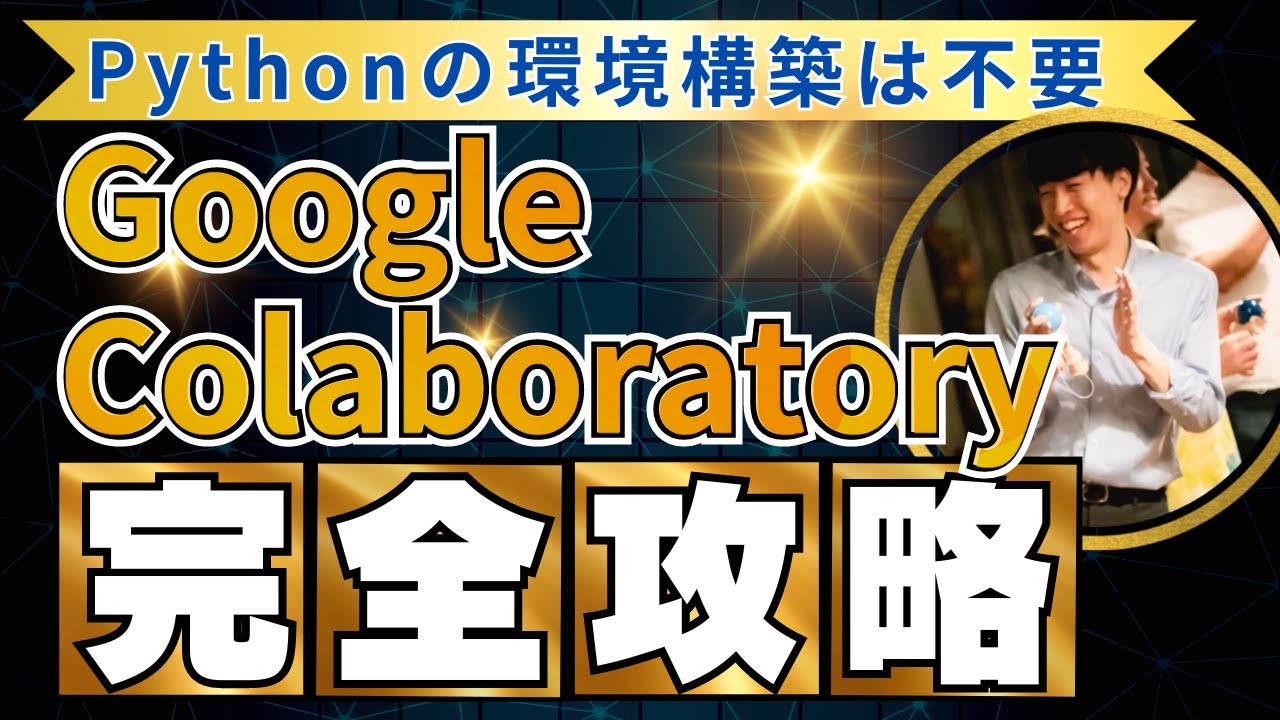


コメント