数学が苦手だと感じている皆さん、ご安心ください!今回の記事では、数学にアレルギーがある方でも、あの東大数学が解けるようになるまでの具体的な道のりをお伝えします。
数学は単なる暗記科目ではありません。むしろ、パズルゲームのように楽しみながら攻略できるものなのです。この動画が提唱する「思考パターン」と「解放パターン」をマスターすれば、どんな難問も解けるようになりますよ。
見どころ
- パズルゲーム感覚の数学学習法: ★★★★★
- 暗記不要の「なぜ?」を追求する学び: ★★★★★
- 東大数学へ繋がる思考プロセス: ★★★★☆
数学は暗記不要のパズルゲームだ!
なぜ数学が苦手になるのか?
多くの人が数学を苦手とするのは、その勉強法が間違っているからかもしれません。例えば、算数の「速さ×時間=距離」の公式を、意味も理解せずに丸暗記していませんでしたか?
高校数学でも同じように、ただ公式を覚えるだけの学習を続けていると、いずれ暗記の限界に達してしまいます。これでは、東大数学のような応用問題は決して解けるようになりません。東大数学を解くには、抽象論思考パターンと解放パターンをしっかりと押さえ、それぞれのパターンに具体的な問題を早起できることが重要なのです。
豆知識: 受験数学の解放パターンは、大学側が「しっかりと勉強してきた学生を選抜したい」と考えているため、基本的に決まっています。つまり、適切な考え方の型を身につければ解けるように作られているのですね!
基本問題を攻略する3つの視点:How、Why、What
「解放パターンが大事なのは分かったけど、まず何から始めればいいの?」そう思われた方もいるでしょう。数学にアレルギーがある方は、まず基本問題のレベルでつまずいていることがほとんどです。そこで、基本問題を解く上で、ぜひ応用問題を見据えた学習をしてほしいのです。
そのためのキーワードが、How(どうすれば解けるのか)、Why(なぜそうしたいのか)、What(どういう問題が解けるのか)の3つです。
How(どうすれば解けるのか):解き方の「要はこうすればいいのね」を掴む
Howは、数学の問題を見たときに、「要はこうすれば解けるのね」という解き方をしっかりと押さえることです。ただし、単に「この問題はこうやって解くのね」で終わってしまってはもったいない!例えば、連立方程式を解く問題で「上の式を2倍して2つの式を足せば解けるのね」と理解するだけでは不十分です。
重要なのは、「2つの係数を揃えて足し引きする」という、より抽象的な解放パターンを掴むことです。基本的な問題集には、同じような大問がずらっと並んでいますよね?それら全てに共通する「要はこういうことなのね」という抽象論を捉えるように意識してみてください。
公式を当てはめるだけの問題もたくさんありますが、これらはまるでゲームの武器集めだと思って楽しみましょう。集めた武器(公式)が多ければ多いほど、入試問題というボスを倒すのが楽になりますよ。
Why(なぜそうしたいのか):暗記不要の「こうしたくなるじゃん」を理解する
Howを抑えた上で、次はWhyです。「なんでこうしたくなるのか」を抑えることで、数学は暗記が不要になります。先ほどの連立方程式の例で考えてみましょう。「係数を揃えて足し引きするのはなぜか?」それは、「だって2文字より1文字の方がいいじゃん」という気持ちになるからなんです。
数学ができる人によくあるのが、「なんでその解法を思いついたの?」と聞くと、「だってこういう時ってこうしたくなるじゃん」と、論理的ではない感情ベースで式変形をする人が多いことです。「こうしたくなるじゃん」と言われてもピンとこないかもしれませんが、普段から抽象論に感情を乗っけてあげることを意識していれば、次第にその感覚が身についてきます。
連立方程式を解くたびに、「いや、これ文字が多いから1文字消していきたいな」という気持ちを持ち続ければ、Howという抽象論を覚えることなく、感情で「こうしたくなる」という実行ができるようになるのです。
What(どういう問題が解けるのか):解ける問題のストックを増やす
そして、意外と忘れがちなのがWhatです。「そもそもどういう問題が解けるのか」を抑えることが重要です。例えば連立方程式であれば、「基本的には連立方程式が解けるんだ」ということを俯瞰して捉えるのです。
このWhatをストックすることによって、応用問題に絶大な効果を発揮します。二次方程式がパッと解けない人がいるとしましょう。ある問題が式変形して、あとは二次方程式を解くだけ、となった時に「うん、これ因数分解できない。因数分解できなかったらどうするんだ…あ、解の公式だったっけな」と、あやふやな状態だと、その問題は「式変形する」「二次方程式を解く」という2ステップの問題になってしまいます。
一方、二次方程式を流れるように解ける人は、そこに追加のステップがないため、その問題はワンステップで解くことができます。このように、「二次方程式は解けるんだ」ということを知っているだけでステップ数が減らせ、応用問題になったときに非常に有利になります。
応用問題では、AしてBしてCしてDして…といったように、ステップ数がどんどん増えていきます。「どういう問題が解けるのか」というストックを増やすことによって、「だからAしてBしてCすればいいじゃん」と、ステップ数を大幅に減らすことができ、結果として応用問題の見通しが非常に良くなるのです。
まとめ: 基本問題を丸暗記するのではなく、まずはHow(要はこうすればいいのね)という思考プロセス(抽象論)を抑える。次にWhy(なんでそうしたくなったのか)という気持ちを抑える。そして忘れがちなのがWhat(どういう問題がそもそも解けるんだっけ)というストックを抑える。この3点セットを意識することが重要です。
これらをゲームの武器集めの感覚で行ってみてください。どんどん強い武器が集まっていけば、入試問題というボスをいとも簡単に倒せるようになるはずです。「また強い武器を集めてしまった!」と楽しみながら学習を進めてもらえたら嬉しいです。
思考プロセスの体系化と問題の言い換え力
How、Why、Whatの3点セットを意識しながら勉強を進めれば、ほとんどの問題は解けるようになるはずです。しかし、ゆくゆくは模試の難しい問題や初見の問題がなかなか解けないという壁にぶつかるかもしれません。そういった時に必要になってくるのが、Howで抑えた思考プロセス、複数の抽象論を組み合わせて体系化する力です。
これは、抽象的な思考が「星」として点々と存在しているのを、それらを線で結んで「星座」を作るイメージに近いでしょう。解けない問題に出くわした時、「この問題、こうやって解くのか」で終わらせずに、「この問題を初見で解ける人は、どういう思考プロセスを辿ったんだろう?」と想像力を働かせることが重要です。
世の中には、問題を初見で見て「こういう風にしたくなるよね」と考える人が実際にいます。その人たちの思考プロセスを追体験していくことが、あなたの数学力を飛躍的に向上させます。この思考プロセスの体系化を自分でできる方は、それだけで数学がめちゃくちゃできるようになりますよ。
もし自分で体系化を行う自信がないという方は、ぜひ高野塾の「徹底基礎講座」をおすすめします。受講完了する頃には、勝手にその思考プロセスが体系化され、あなたの脳内にインプットされています。
東大レベルの難問を解く「言い換え力」
さらに先の話になりますが、東大のような難関大学になると、一見全く見たことのないような、パターンから外れてそうな問題も出題されます。そんな時に必要になってくるのが、問題を言い換える力、つまり「要はこういうことか」と咀嚼する力です。
全然問題設定を見たことがなくても、実験などを繰り返していくと、「この問題設定って、要はあの典型問題と同じことやってるじゃん!」という風に気づけることがあります。そこからパターンに落とし込んで、問題を解くことができるようになるのです。
このような問題も解けるようになりたければ、日頃から「ああでもない、こうでもない」とトライアンドエラーを繰り返しながら手を動かす経験が非常に重要になってきます。難問に出くわした時に、すぐに答えを見るのではなく、1時間でも2時間でも粘ってみる経験も大切ですよ。
とはいえ、このレベルは東大数学の中でも周りに差をつけたいという上積みの話です。まずは目先の問題集で、How、Why、Whatの3つのポイントを意識してもらえれば大丈夫です。
徹底基礎講座で数学の壁を打ち破ろう!
今回お話しした道筋を一歩一歩進んでいけば、数学が苦手な状態から、東大数学にも立ち向かえる数学力が身についてくるはずです。この道筋を爆速で駆け上がっていきたい方は、「徹底基礎講座」がおすすめです。
徹底基礎講座は、ゲト塾長自身の数学力の全てを濃縮した、ゼロから全ての大学に通用する数学力が身につく講座です。演習量も豊富で、さらにその演習一つ一つに「なぜその問題が解けるのか」という思考プロセスが言語化され、皆さんに伝授されます。そのため、問題演習を一通り終える頃には、勝手に論理的な思考プロセスがあなたの脳内にインプットされているのです。
実際に受講者の中には、数学が苦手だったのに1年間徹底基礎講座を信じて学習してもらった結果、東大模試で数学で冊子に載るくらい得意になった方もいるほどです。ぜひ、徹底基礎講座を信じて、あなたの数学力を開花させてみませんか?
数学で必要な論理的思考力や問題解決能力は、数学に限らず、人生全てを豊かにしてくれるものです。「今後の人生を豊かにしていくぞ!」という気持ちで、数学も勉強してもらえたら嬉しいです。ぜひ、高野塾の徹底基礎講座で一緒に合格を勝ち取りましょう!

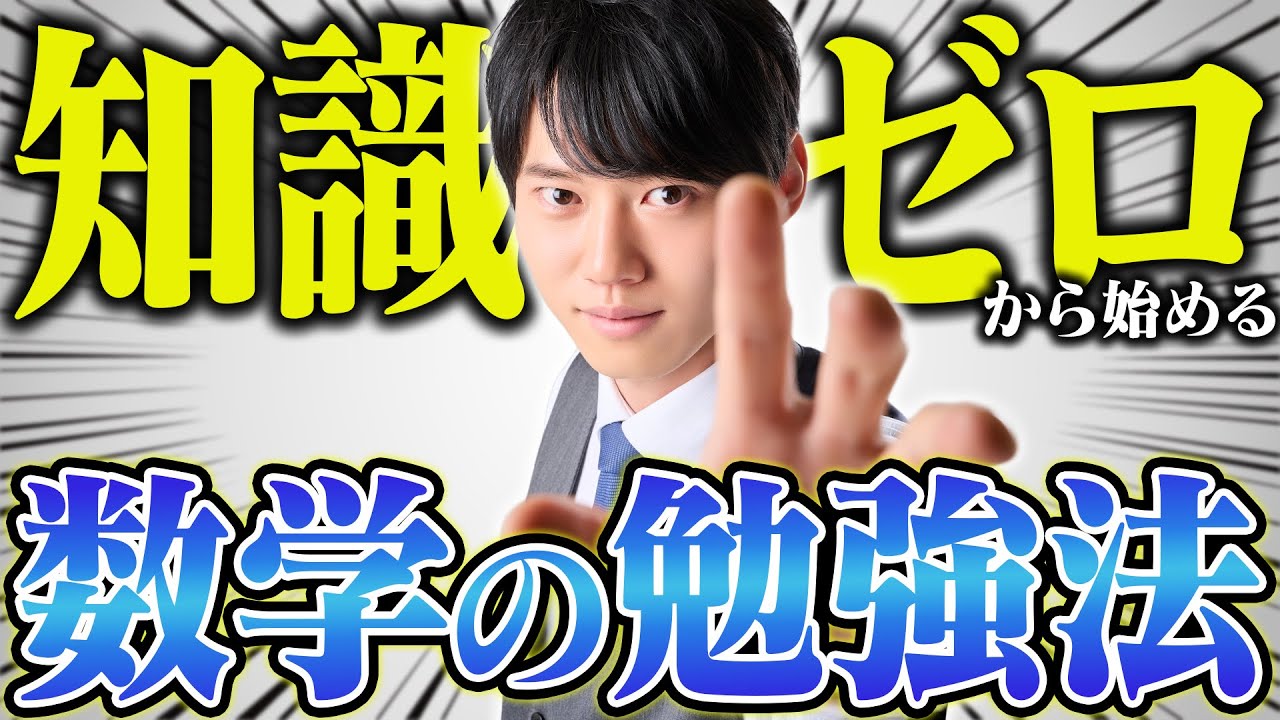


コメント