皆さん、こんにちは!「図形の性質はセンスが必要だ…」そう思ってはいませんか?共通テストやセンター試験の過去25年分を徹底分析した結果、その考えは完全に覆されます。
まさに「センス不要の完全解」を手に入れることができるでしょう!
見どころ評価
- 解説の分かりやすさ:★★★★★
- 実践への応用性:★★★★☆
- 網羅性:★★★★★
図形の性質、苦手意識を克服する3つのストック
図形の性質の問題で「自分にはセンスがない」と落ち込んでいた方、もう心配はいりません。この動画を最後まで見れば、これまで図形の性質に対して向き合っていた方法が根本的に間違っていたことに気づくはずです。
図形の性質を攻略するためには、以下の3つのポイントをストックすることが非常に重要です。これらをしっかりと抑えれば、共通テストのどんな問題も再現性を持って解けるようになります。
- 場面ごとに使える「武器」:どんな状況でどの定理や公式を使えば良いか
- 「よくある図形」のパターン:頻出する図形の特徴とそれに対するアプローチ
- 共通テストの「よくある流れ」:問題の誘導パターンと解答戦略
この3つのストックがあれば、皆さんはもうセンスに頼る必要はありません。後ほど過去問3年分を爆速解説しますが、その中で「本当にこの3つを抑えれば全部解けるようになるんだ!」と実感していただけるはずです。
場面ごとに使える武器:円と長さ・角度
図形の問題に遭遇した際、「この図形はどの場面に当てはまるだろう?」という抽象的な思考が非常に重要です。例えば「円が絡む長さの問題だ」と判断できれば、そこから使える武器を連想し、具体的な図形をいじっていくというステップを踏むことができます。
円が絡む長さの問題
円が出てきて、その中の長さを考える場合、主に以下の3つの武器を連想しましょう。
- 方べきの定理:円と2本の直線に関する定理です。円の内部で交わる場合も、外部で交わる場合も、接線の場合も適用できます。
- 90°から直径の連想:円の中に直角三角形がある場合、その斜辺が円の直径になっている可能性が高いです。直角を見たら常に直径を意識しましょう。
- 相似の利用:円周角の定理などにより、等しい角がたくさん出てくる円では、相似な図形を見つけやすいです。
豆知識: 方べきの定理は、実は相似な三角形を利用して証明できます。例えば、2本の直線が円の内部で交わる場合、補助線を引くことで2つの三角形が相似になり、そこから方べきの定理が導かれます。定理だけでなく、その成り立ちを知ることで、より深く理解できますね。
円が絡む角度の問題
円が絡む角度に関する問題では、以下の3つの武器が役立ちます。
- 円周角の定理:同じ弧に対する円周角は等しい、中心角は円周角の2倍など、円周角に関する基本定理です。
- 四角形の対角:円に内接する四角形の向かい合う角の和は180°です。また、外角が内対角に等しいという性質も重要です。
- 接弦定理:円の接線と弦がなす角は、その弦が作る弧に対する円周角に等しいという定理です。これは円周角の定理や四角形の対角の性質から考えることもできます。
ちょっと一息: 接弦定理を忘れがちな方は、円に内接する四角形の性質から導き出す方法を試してみてください。視覚的に理解することで、記憶に残りやすくなりますよ。
円の接線が出てきたら
円の接線が登場した場合は、以下の点を連想しましょう。
- 方べきの定理や接弦定理などの公式
- 中心と接点を結ぶと垂直になる(半径と接線は直交する)
- ある点から引いた2本の接線の長さが等しいという「よくある形」
長さの比を求める場合:角の二等分線とチェバ・メネラウスの定理
長さの比を求める問題では、主に以下の2つのパターンを連想すれば大丈夫です。
- 角の二等分線:内角の二等分線であれば、AB:AC = BD:DC。外角の二等分線も同様の関係が成り立ちます。
- チェバの定理・メネラウスの定理:これらは図形の比に関する非常に強力なツールです。
豆知識: 角の二等分線上にある点から2本の直線までの距離は等しいです。この性質が、内心が角の二等分線の交点であることと繋がっています。重心(中線の交点)は2:1に内分する点、外心(各頂点からの距離が等しい点)は辺の垂直二等分線の交点といった関連知識も確認しておくと良いでしょう。
チェバの定理とメネラウスの定理
これらの定理は、複雑な公式を覚える必要はありません。「三角形一周旅行、ただし分点を通る」という考え方をすれば、簡単に式を導き出すことができます。
- チェバの定理:三角形と「点」に関する定理です。3つの直線が1点で交わることを確認する際に役立ちます。
- メネラウスの定理:三角形と「直線」に関する定理です。3点が一直線上にあることを確認する際に役立ちます。
どちらの定理も、始点から三角形の辺を辿り、分点(直線と辺の交点)を経由しながら一周するイメージを持つと、式をスムーズに立てられます。どの三角形を一周すれば良いか迷ったら、「分かっている長さの比」と「求めたい長さの比」が絡む線分を含む三角形を選びましょう。
よくある図形と逆の活用
共通テストでは、頻繁に登場する特定の図形パターンがあります。これらをストックしておくことで、問題を見た瞬間に「あのパターンだ!」とひらめき、迅速に解答へと導くことができます。
よくある図形のパターン
- ある点から引かれた2本の接線:この場合、その点から各接点までの距離が等しくなります。これを応用すると、直角三角形の内接円の半径を素早く計算できたりします。
- 向かい合う角が共に直角の四角形:このような四角形は円に内接します。対角線の中点がその円の中心になります。直角を見たら、円に内接する四角形を連想できるようになりましょう。
- 2つの直角三角形:特定の条件下で2つの直角三角形が相似になるパターンもあります。これも知っておくと、時間短縮につながります。
逆の活用:4点が同一円周上にあるか?
「4点が同一円周上にあるか?」という問題は頻出です。これを確認する際には、以下の「逆」を活用しましょう。
- 円周角の定理の逆:2つの角が等しければ、それらの角の頂点を含む4点は同一円周上にあると言えます。
- 四角形の対角の性質の逆:向かい合う角の和が180°であれば、その四角形は円に内接します。
- 方べきの定理の逆:長さの関係式が成り立てば、4点は同一円周上にあると言えます。
角度から攻めるか、長さから攻めるか、問題の状況に応じて使い分けましょう。
さらに逆を考える: チェバの定理の逆は、3つの直線が1点で交わることの証明に、メネラウスの定理の逆は、3点が一直線上にあることの証明に役立ちます。応用問題で差がつくポイントなので、頭の片隅に入れておきましょう。
共通テストの出題あるあるパターン
共通テストの図形の性質には、特定の出題パターンがあります。これを知っておけば、問題の誘導に乗っかりやすくなります。
出題あるあるパターン
- 微妙に設定を変えてくるパターン:例えば、問1で鋭角三角形の場合を、問2で鈍角三角形の場合を考えるなど、似たような状況設定で少しだけ条件を変えてくることがあります。この場合、問1の考え方が問2にどこまで通用するのかを常に意識することが重要です。
- 謎の式を求めさせるパターン:「この式が成り立つことを示せ」といった、一見すると何の役に立つかわからないような式を求めさせることがあります。しかし、このような式は問2以降で大活躍することがほとんどです。謎の式が出てきたら、「きっと後で使うんだな」と心に留めておきましょう。
過去問解説:ストックの力を実感しよう!
これまで解説してきた3つのストックを実際に活用しながら、過去問3年分(2021年、2022年、2023年)を徹底的に解説していきます。この解説を通して、皆さんがストックの重要性を肌で感じ、共通テスト本番に自信を持って臨めるようになることを願っています。
2021年の問題:図形を丁寧に書くことがカギ
この年の問題では、図形をいかに大きく、そして丁寧に書けるかが重要でした。一見複雑に見える問題でも、状況を正確に把握できれば、これまで紹介した武器を適切に適用して解くことができます。例えば、角の二等分線の性質や方べきの定理、相似などを使いこなせば、スムーズに解答にたどり着けたはずです。
特に、4点が同一円周上にあるかを確認する問題では、方べきの定理の逆を適用することで、瞬時に正誤を判断することができました。このように、自分の武器をストックしておくことで、様々なアプローチで問題に挑むことが可能になります。
2022年の問題:謎の式が大活躍!
「非常に難しかった」と評価された2022年の問題ですが、これも1つ1つ丁寧に考えていけば解ける問題でした。特にポイントとなるのは、共通テストあるあるの「謎の式を求めさせるパターン」です。
問題の序盤で出てきた一見意味不明な長さの関係式が、後半でAPやAQの長さを求める際に大活躍しました。チェバの定理やメネラウスの定理を適切に使いこなし、得られた謎の式を有効活用することで、多くの受験生が苦戦したであろうこの問題もクリアできます。「この式、何かに使えるはずだ!」という意識が重要だったのですね。
2023年の問題:誘導に乗れば難しくない!
この問題も非常に良問でした。共通テストの「微妙に設定を変えてくるパターン」が顕著に現れており、問1で得た知見が問2にどこまで通用するのかを考える力が問われました。
特に、「4点が同一円周上にあること」の証明では、角度からのアプローチ、つまり円周角の定理の逆や四角形の対角の性質の逆を適切に使うことで、迷うことなく解答にたどり着けます。また、後半の長さの問題では、直角が多数登場することに気づけば、直径や三平方の定理を活用してスムーズに解答できます。
いかがでしたでしょうか?今回解説した過去問を通して、3つのストックがどれほど強力な武器になるかを実感していただけたかと思います。
共通テストの図形の性質は、決してセンスだけで決まるものではありません。適切な知識をストックし、問題のパターンを見抜く力を養えば、誰でも攻略できます。この動画で話した内容を何度も復習し、しっかりと自分のものにしてください。
皆さんが共通テスト本番で最高のパフォーマンスを発揮できるよう、心から応援しています!

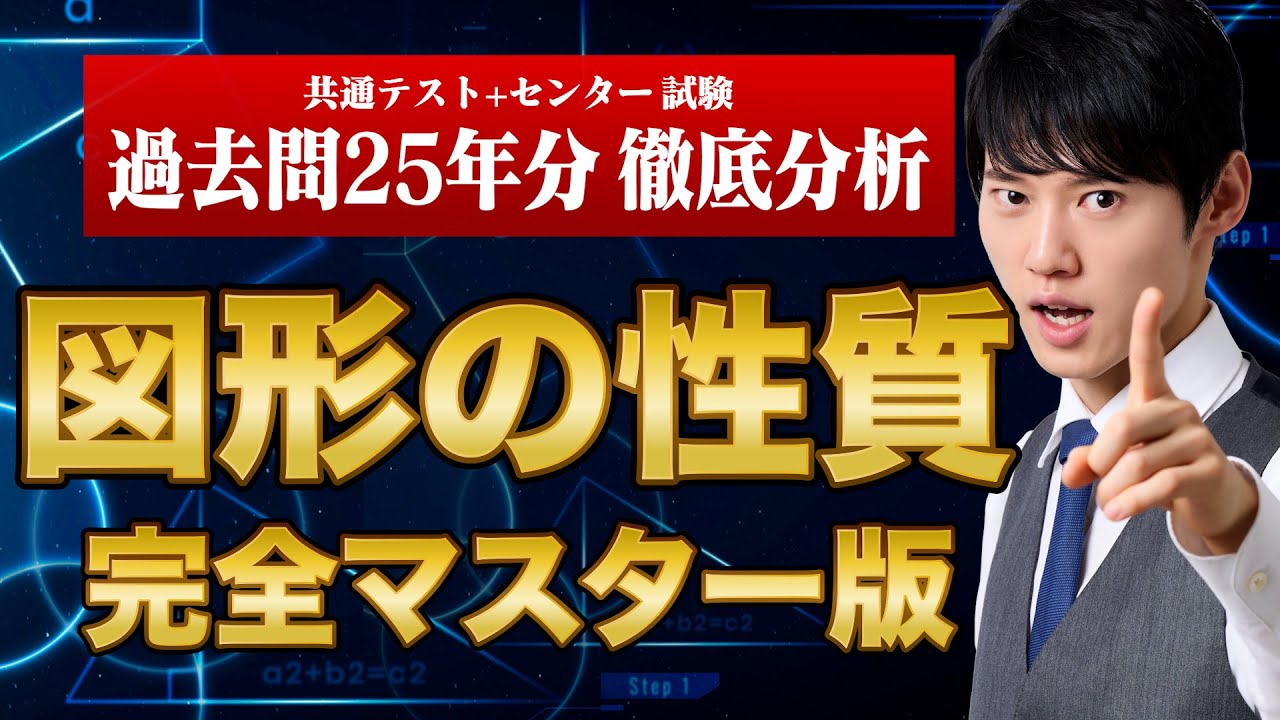


コメント