今や私たちの生活に欠かせない存在となったAI。その進化は、ビジネスの世界にも大きな変革をもたらしています。特に、コンサルティング業界のような知的労働の現場では、AIによって仕事のあり方が根本から変わりつつあると言われています。かつてマッキンゼーという超一流の舞台で、昼夜を問わず仕事に明け暮れた南場智子氏と、その先輩にあたる茂木氏。二人の対談から見えてきた、AI時代に求められる人材像とは?そして、スタートアップや日本経済の課題を乗り越えるためのヒントとは何でしょうか?
この記事は、キャリアに漠然とした不安を抱えるすべての人に向けた、未来を生き抜くための羅針盤です。AIをただのツールとしてではなく、自分の可能性を広げるパートナーとして捉え、自ら道を切り拓く勇気を与えてくれるでしょう。さあ、一緒に新しい時代の働き方を探求してみませんか?
見どころ
- マッキンゼー時代の衝撃的な働き方:★★★★★
- AIが変えるキャリアパスと組織:★★★★★
- 南場氏が語る人生の優先順位:★★★★★
今では考えられないような「超ブラック」だったというマッキンゼー時代。当時の過酷な働き方を知る南場氏と茂木氏は、AIの進化がその「下積み」を不要にし、よりフラットな組織を作り出す可能性を語ります。これは単に労働環境が改善されるという話ではありません。
AIを使いこなせる人とそうでない人の間に新たなヒエラルキーが生まれ、個人の生産性に圧倒的な差がつく時代が来ているのです。あなたのキャリアは、AIをどう活用するかによって大きく変わるでしょう。その覚悟はできていますか?
AIの進化が変えるコンサルティング業界
1980年代、南場氏がマッキンゼーに入社した頃は、長時間労働が当たり前の時代でした。徹夜は日常茶飯事で、茂木氏によれば「今の労働基準法では考えられない」ほどのブラックな環境だったといいます。当時、新人コンサルタントは、膨大な資料の読み込みや、電話を使った情報収集など、地道で時間のかかる作業に多くの時間を費やしていました。
しかし、時代は変わりました。インターネットの登場で情報収集は格段に楽になり、さらに現在はAIがその仕事を代替する時代へと突入しています。AIはもはや、単なるリサーチツールではありません。同僚AI(AIエージェント)は、夜間に数十のタスクをこなし、朝までにはその結果をまとめてくれる、まるで自分の分身のようです。これにより、かつて何年もの下積みを要した作業が、数か月でできるようになるかもしれません。
茂木氏は、このようなAIの進化が、これまでの階層的な組織(アナリスト、コンサルタント、マネージャーなど)を、よりフラットな組織へと変えていく可能性を指摘します。個々の能力が際立つようになり、できる人は早めに頭角を現すことができるようになるのです。
豆知識:
AIは今、建築や医療など、フィジカルな要素が強い現場にも進出し始めていますが、茂木氏曰く、タイムラグがあるため、当面はAIが代替できる仕事と、人間の経験や判断が必要な仕事との二極化が進むだろうとのことです。
日本経済の停滞とスタートアップの課題
対談では、AIの話から派生して、日本の経済全体が抱える構造的な問題にも話が及びました。茂木氏は、日本の人材がエンゲージメント(仕事への愛着)が低いにもかかわらず、独立や転職への意欲がなく、スキルアップのための努力も怠っている現状を指摘します。その結果、経済全体が活力を失っているというのです。
南場氏もこれに同意し、日本の経済は「ダイナミズム(活力)の欠落」が最大の問題だと語ります。アメリカでは、トップ企業が常に新陳代謝を繰り返し、新しいプレイヤーが次々とトップ10に入ってくるのに対し、日本ではここ20年ほど、ランキングに大きな変動がありません。これは、新しい産業や企業が育ちにくいことを示しています。その原因として、以下の2つが挙げられました。
- 資金調達の難しさ:アーリーステージのベンチャーキャピタルは増えたものの、それ以前のエンジェル投資家や、レイターステージの大型投資家が少ないため、資金繰りに苦労するスタートアップが多いのが現状です。
- 人材の流動性の低さ:大企業が優秀な人材を囲い込み、転職や起業が当たり前という文化が根付いていないため、人材がイノベーションが起きやすいスタートアップに流れにくい。
これに対し、茂木氏は、個人が保有する2200兆円もの金融資産や、企業が持つ300兆円の内部留保が、もっとスタートアップに流れるような仕組みが必要だと主張しました。また、南場氏も、「張り切った人が報われる社会」にすることが、日本経済を活性化させる鍵だと語っています。
ビジネスも人生も、優先順位がすべて
DeNAを立ち上げ、まさにビジネスが軌道に乗ろうとしていたタイミングで、南場氏の最愛のパートナーが病に倒れました。そこで南場氏は、ビジネスの一線から身を引き、看病に専念することを決意します。この決断に迷いはなかったのでしょうか?
南場氏は「正直、あまり迷いはなかった」と語ります。それまで最優先だったビジネスが、パートナーの健康という「喫緊の課題」に取って代わったからです。世の中の経営者には、自身の健康を理由に引退する人はいても、配偶者の健康を理由に辞めた人はほとんどいませんでした。この無責任な決断だと承知しつつも、迷うことなく看病に専念したそうです。
パートナーは5年半という余命を宣告されながらも、その期間を懸命に生き抜きました。南場氏はその日々を振り返り、「普通の健康な時よりも、人のありがたみが身にしみた」と語り、とても濃密で幸せな時間だったといいます。このエピソードは、人生の優先順位を明確にすることの重要性を私たちに教えてくれます。どんなに成功を追い求めても、本当に大切なものを失ってしまっては意味がありません。
最後に、お二人の話から、これからの時代を生き抜くためのヒントが見えてきました。AIを味方につけて自分の生産性を高め、世の中の常識や「正解」に囚われず、自ら「本物の打席」を見つけること。そして、自分の情熱とやりがいを大切にしながら、ビジネスだけでなく人生そのものを豊かにすること。これらの教えは、AI時代を生き抜くための、最高の羅針盤となるでしょう。


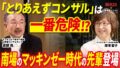

コメント