文学界の最前線で活躍する編集者が語る、ベストセラーの裏側と文学賞の知られざる関係。売れる作品と評価される作品の間に横たわる深い溝、そして「才能」という摩訶不思議な存在に迫ります。果たして、真の傑作とは何か?そして編集者の役割とは?
★識者による5段階評価★
- 才能の深掘り度:★★★★★
- 編集者の情熱:★★★★☆
- 読者の共感度:★★★★☆
私たちが何気なく手に取る一冊の本に、どれほどのドラマが詰まっているのか、ぜひこの機会に感じ取ってください。
文芸界のリアル:売れる本と評価される本のギャップ
文芸の世界では、世の中で「売れる本」と「文学賞で評価される本」が必ずしも一致しないという、編集者にとっては悩ましい現実があります。特に、芥川賞や直木賞といった権威ある賞は、時に作品の「良さ」とは異なる基準で選考されることがあるといいます。
「賞を取っているものが、良い作品とも限らない」という衝撃的な発言も飛び出しました。これは、賞にはその賞なりの「らしさ」があり、そこにフィットする作品が受賞するという側面があるからだそうです。例えば、直木賞には「直木賞っぽさ」というものが存在し、選考委員はその基準で作品を選びます。そのため、良い作品だから直木賞を獲れる、という単純なものではないのです。
この状況は、作家だけでなく、実は編集者をも飲み込んでいくことがあります。担当する作家の作品を賞に導きたいという気持ちが強くなるあまり、知らず知らずのうちに「賞を獲る」ことが目標になってしまうケースも少なくないようです。
豆知識:村山由佳さんの小説「プライズ」は、直木賞を熱望する作家の姿を描いた作品で、賞の持つ危うさや、それに翻弄される人々の姿がリアルに描かれています。この作品を読むと、文学賞の光と影がより深く理解できるかもしれません。
「溢れ出す才能」と編集者の役割
文芸編集者として長年活躍する中で、彼がたどり着いた「才能」の定義は非常にユニークです。それは、藤田真央さんや宮島未奈さんのように、「ご本人の中から言葉や表現が溢れ出している人」のことだと言います。「才能がある人って、こぼれちゃってるんだと思う」という言葉には、その天才たちの持つ圧倒的なエネルギーが凝縮されています。
例えば、世界的なピアニストである藤田真央さんの著書「指先から旅をする」の制作秘話は、まさにその「溢れ出す才能」を象徴するエピソードでした。フランスでの撮影時、予定していたピアノが急遽使えなくなるというアクシデントに見舞われます。しかし、藤田さんの音楽に対する現地の人々のリスペクトと、彼の愛され方が相まって、なんとコンサートで使用する大切なピアノを、30分後という直前にもかかわらず森の中に運び出してくれたというのです。
これは、藤田さんの才能が周囲の人々を動かし、不可能を可能にする力を持っていることを示しています。彼の演奏は、マルタ・アルゲリッチの代役を完璧に務め上げ、聴衆に「来年は真央の曲を聴きたい」と言わしめるほど。これはまさに「天才」としか言いようがありません。
また、宮島未奈さんの「婚活マエストロ」についても触れられました。「成瀬は天下を取りに行く」で大ブレイクした宮島さんですが、彼女もまた「作品をもう一作読みたいと思わせる作家さん」であり、その才能は尽きることがありません。
編集者の使命:溢れる才能をパッケージ化する
では、そのように「溢れ出す」才能を持つ作家たちに対して、編集者はどのような役割を果たすのでしょうか。それは、「その溢れてるものをパッケージ化して、人が咀嚼しやすいものにする」ことだと編集者は語ります。しかし、この作業はともすると才能を「矮小化」してしまう危険性もはらんでいます。
濃い味付けにしたり、つまらない味付けにして出してしまうことや、前回と同じような方法でまとめてしまい、結果的に面白くないものにしてしまうこともあり得るのです。だからこそ、編集者としては「つまらない本ができたら、自分の責任だな」という強い責任感を持って仕事に臨んでいます。
豆知識:アメリカの著名な編集者であるマックスウェル・パーキンズは、「編集者は常に正しい(The editor is always right)」という言葉で知られています。F・スコット・フィッツジェラルドの「グレート・ギャツビー」の編集においても、パーキンズは大胆なカットを行ったと言われています。しかし、日本の編集者の多くは、作家の意向を尊重し、あくまで「ご提案」という形で意見を伝えることが多いようです。
作家と編集者の関係は、時に激しい議論を伴うこともあります。しかし、最終的に作品の責任は作家にあり、その名前で世に出る以上、作家自身が納得して決めるべきだという考え方が根底にあります。編集者は、納得感のある答えを導き出すまで、作家と共に走り続ける「伴走者」のような存在なのかもしれません。
日本文学の現在地とグローバルな視点
近年、日本文学は海外での受容に変化が見られます。特に女性作家の作品が海外で注目を集めていますが、そこには「オリエンタリズム」という視点が強く求められすぎている現状も指摘されています。
村田沙耶香さんの「コンビニ人間」や川上未映子さんの作品など、日本で高い評価を得ている作品が海外でもヒットしていますが、それらの作品が「オリエンタリズム」という言葉で語られることが多いことに、編集者は疑問を呈しています。作品が持つ本来のテーマとは異なる文脈で評価されることは、必ずしも幸福なことではないのかもしれません。
一方で、茂木健一郎氏の「IKIGAI」がドイツで売れている背景には、AI時代における人間のウェルビーイングの追求という、新たな文脈があることも示唆されました。これは、禅の思想とはまた異なる、現代的な課題意識に基づいた受容のされ方と言えるでしょう。
ジェンダー視点と日本文学
村上春樹作品の海外での受容についても、ジェンダー論的な視点から変化が見られるという意見が提起されました。しかし、これは海外での変化というよりも、日本国内でジェンダー論的な読み方が浸透してきた結果、村上作品の読み方も変わってきたように感じられるのだと編集者は分析します。日本国内の変化が、海外よりも10年ほど遅れて起こっているという指摘は、現代の日本文学が抱える課題の一つなのかもしれません。
昨年イギリスで大ブレイクした柚木麻子さんの「BUTTER」は、女性の欲望をテーマにした作品ですが、日本ではその生々しさゆえに、本来もっと売れても良いはずの作品が、思ったよりも伸びなかったという現実があります。これは、センセーショナルなテーマが敬遠される傾向や、小説から現代的なテーマを読み取るという行為自体が、まだ日本には不足しているためではないかという、厳しい見方も示されました。
豆知識:ヴァージニア・ウルフの「灯台へ」は、世界中で愛されるモダニズム文学の傑作ですが、日本ではまだその読み方や意義が十分に共有されていないという課題があるようです。出版社側が、古典や海外文学を「なぜ今読むべきなのか」という補助線を引く努力が、今後さらに求められることでしょう。
しかし、安堂ホセさんの「DTOPIA」が芥川賞に選ばれるなど、多様なテーマを扱う作品が評価される土壌も着実に育ちつつあります。芥川賞は、現代的なテーマや、今を生きる私たちにとって切実なテーマをすくい上げる役割も果たしているのです。
本のマーケットがグローバル化する中で、日本文学は「日本語」という枠に守られてきた側面がある一方で、ビジネス的には厳しい状況にあります。文体の美しさや精緻さといった従来の価値観だけでなく、文学の本質的な面白さや、読者にとっての意味が求められる潮流です。


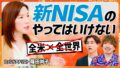

コメント